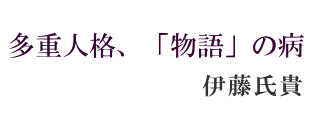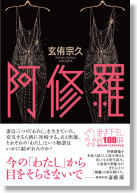|
|||
| 東京、九州行脚を終え、無事に興福寺に還った阿修羅像は、日本中に一大ブームを巻き起こした。だが、この度の展覧会以前でも興福寺に行きさえすれば拝めたこの像に、なぜ東京だけで百万に近い人間が群がったのか。 それは、これまで壁を背にしていたため観えづらかった残るふたつの貌とも正対できるよう、全方位展示になったからだ。こうなると既に観たことのある人でも、というより既に観てその魅力に憑かれた人こそ、正面以外の貌もじっくり観たいという欲望を喚起されずにはいられない。それは、別のじぶんに出会いたいという欲望のあらわれにも思える。 別のじぶんが勝手に外に出てくると、それをわれわれは「解離」という「障害」として病のなかにくくる。とすれば阿修羅像は三重人格の表象なのか。たとえば本作の「実佐子」の中には実佐子自身の知らない人間が最低でも二人いる。いわゆる解離性同一性障害だ。夫はじぶんの知らない妻の「貌」にでくわして動揺を隠せない。「貌」が変わるとは比喩ではなく、表情から姿勢、体型、胸の張りまでが実際に人格ごとに変わって見える。玄侑は実際にこの病を病む人間と出会ったと言うが、たしかに取材は詳しい。読めば実佐子のことが他人事とは思えなくなる。 われわれ自身も時と場合によって意図的にあるいは自然に貌を使い分けているのではないだろうか。最近は、その使い分けがうまくできない人間を「KY」と呼んで蔑みさえするのではないだろうか。阿修羅展に足を運んだ者が皆そこに救いを求めに行ったとは考えがたい。救いを探すなら美術館より寺の方がよいに決まっている。となれば、この阿修羅人気は、縋るべき超越者をではなく、じぶんがそうなりたい理想の姿を求めているということではないだろうか。 この病をモチーフあるいはテーマとした小説は少なくない。『ジキル博士とハイド氏』は言うに及ばず、ドストエフスキーの『二重身』や芥川の自己像幻視はこの障害の一症状とも考えられる。最近では阿部和重もこの病を患っているとおぼしき主人公を描いている。しかしかれらが基本的に人格の多重化をきわめて異常な、あるいは超自然的な体験として描くのに対し、玄侑は、いささか踏み外しつつも正常に回収しうるものとして、言いかえれば日常の延長として捉えている。人格を分裂させた当人の困惑・混乱を内側から描くのではなく、日常の側にいる者がそれを外から客観的に見つめ、なんとか日常という名の毛布でくるみこもうとする。 たしかにそれは簡単なことではない。実佐子の分裂を受け入れられない夫は現実から逃避しようとするし、医者でさえ「憑依」という超自然的な語彙に絡めとられそうになる。しかしそれでもかれらは分裂した人格を見放さない。あくまでじぶんたちは日常の側に踏みとどまって、それぞれの人格と対話をつづける。そしてそれ以上のことは基本的にしない。ある人格を呼び出すときに催眠法を用いたりはするものの、それが交代人格を抹殺するために使われたり、あるいは薬物の類が投与されたりすることもない。最大にして唯一の薬は「ことば」なのだ。それは、この病が「物語」の病だからだ。 ひとつめの人格がじぶんの物語の重圧に耐えきれなくなった時、じぶんの体験から違う記憶を拾って新たに紡がれた別の物語を生きる第二の人生が生まれる。それでも耐えきれなければ第三の……。だから、仮に一見対立するように見えても、かれらは第一の人格にとって必要だからこそ生みだされたのであり、ある意味では第一の人格の支えでもあるのだ。単純にかれらを封印し圧殺するだけで事足れりとするわけにはいかない。それぞれの人格が別々に分けもっている記憶を共有させ、その後かれら自身の間で話し合いをさせなければならない。医師はそのとき通訳であり、話し合いの「場」そのものになる。人間にとって「日常」とは「話し合いの場」なのだと言いかえてもよい。われわれは貌と貌をつきあわせて互いとことばを交わし、そのなかで「じぶん」を確立する。しかし阿修羅像の貌がそれぞれ一二〇度ずつそっぽを向いて決してお互いを見交すことができないように、分裂した人間同士もうまくお互いに会話することができない。だから「病」とされるのだ。 さてしかし、となると阿修羅人気は病への憧れということになるのだろうか。そうではあるまい。阿修羅当人にとってはできないことなのだが、われわれはかれの三つの貌を見比べることができる。われわれが密かに憧れているのは、いくつもの貌を持ちつつもそれぞれの別の記憶=物語に支配されない状態なのではないだろうか。鬩ぎ合わずいくつもの貌を着こなすなら、多重人格は「病」でも「障害」でもなくなる。作中でも「経歴ってのは、いつだって物語」だと言われている。われわれがわれわれであるのはその経歴というフィクションの紡ぎ方によるのだ。ではそれを状況に応じてほどいては紡ぎ直すことは可能だろうか。 可能だとしても、それはたんなる「演技」になってしまうようにも思える。要は「裏表の激しい人間」になるだけでないのか。結局われわれにとって阿修羅とはなんなのか。 玄侑はそれがわれわれの誰の内にもあるなにかだと最後に示唆するにとどまるが、ここに新たな可能性を見ることもできる。なぜそもそも分裂は統合されねばならないのか。AとBとCに対する時では、それぞれ違った貌を持っていてもよいのではないか。それが「嘘も方便」ということなのではないか。しかし、われわれはどうしてもじぶんの核のようなものを求めてしまう。近代がそれを「個性」という語で称揚して以来、われわれは核へ執着し、そしてそろそろ疲れてきたのではないか。そこから解放されたいという願いこそが、阿修羅への憧れを駆り立てるのではないか。玄侑も一僧侶の口を借りて言う。「状況に応じて人は幾つもの顔を使いこなす」「『ほんとうの自分』など邪魔になるから措定すべきではない」と。実佐子の分裂に戸惑いながらも、医師たちはそれぞれの人格にそれぞれの魅力をたしかに感じていたではないか。 もしわれわれがこの意味で近代すなわち「ほんとうの自分」を乗り越えたらどうなるのだろうか。阿修羅たちが蠢く街の出現。これ以上の具体的イメージは示せないが、少なくともその街への移住希望者たちが阿修羅人気を支えていくことはまちがいない。 |
|||
 |
|||
| 「文學界」2010年2月号 文學界図書室 | |||
| |
|||