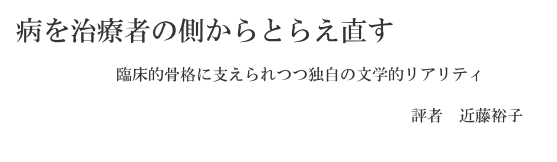|
||
| 古くは『イヴの三つの顔』、新しくは『24人のビリー・ミリガン』の衝撃以来、「解離性同一性障害」は、「多重人格」という鮮烈なイメージの言葉に置き換えられ、「トラウマ」や「幼児虐待」と言った分かりやすい物語と結託しつつ、私たちの目を奪い続けてきた。けれど、私達が興味をそそられていたのは、年齢も性別も能力さえも全く異なる人格に、一人の人間が瞬時に入れ替わるという、その症状の華やかさにだったのではないだろうか。 玄侑宗久の『阿修羅』は、この解離性同一性障害という病を扱いつつ、中心的な語り手の一人に杉本という精神科医を据え、脇にも臨床心理士やそれを目指す大学院生(杉本の娘)、さらには異なる見解をもつ別の精神科医らを配すことで、病を治療者の側からとらえ直すことに努めた。 私達読者は、杉本の専門家ならではの思考や、彼が同僚・娘らとかわす言葉を通して、解離という病がどういう人間関係の軋みから生じやがて重症化してゆくのか、病者とその家族にはどのような混乱と痛苦をもたらすのか、そしてどういった治療プロセスを経て回復へと導かれてゆくのかを丁寧に辿ってゆくことができる。そこで私達が体験するのは、好奇をそそる既成の「多重人格」イメージの修正であり、それが私達にもありえた、あるいはありうるかも知れない事態だったという気づきである。それは、人格をとらえる際に陥りがちな「正常・異常」という二分法を組み替え、「ほんとうの自分」とは何なのか、そもそもそのようなものがあるのかという思索へと誘ってゆく。 杉本は、三つの異なる人格に分離している患者実佐子の病を、治療的関与が必要な人格崩壊の危機ととらえている。しかし、だからといって彼の治療の目標として、単一不変の「自我」が見据えられているわけではない。それぞれの人格が分け持ってきた記憶を共有し、納得の行く一つの物語がつむがれたときに「自己という纏まり」は立ち上がってゆくのだと杉本は言う。 彼が「自己」を語るときに繰り返す特徴的な言葉が、この「物語」である。放っておけば消えてしまうかも知れない記憶が誰かに語ることで補強されるように、あるいはいくつもの記憶の小筋が語りと共に合流してゆくように、自己とはひとつのまとまりとして語り果せた言葉の河のようなものなのかもしれない。 そしてもう一つ彼に特徴的なのは、人は諸関係の中で相異なるさまざまなありよう(側面)を生きるという捉え方である。この異なる側面が結晶化したものが人格だとすれば、「多重人格」と呼んでいた「異常」も、「父」(家族役割)や「医師」(職業役割)や「男」(ジェンダー)といった諸関係からの異なる(時に矛盾する)要請を生きる私たちの「正常」の延長線上に見えてくるはずだ。 杉本は、治療に際して治療者と患者との間に信頼関係を築こうとするのだが、実佐子が辛い記憶を遡ってゆくためには、治療という関係に信頼と安心を感じとっていなければならない。回復もまたそうした関係の土壌から芽生えて行く。 しかし本作の力は、こうした臨床的骨格に支えられながらも、なおその枠組みを踏み越え独自の文学的リアリティをつむぎ上げてゆくところにある。 杉本に支えられつつ記憶を遡る実佐子の語りは、「もうひとりの自分」が出現する瞬間に至る。中学生だった彼女は、思いを寄せる相手からもらった蛍を、取り巻きの同級生たちに圧され、彼の目の前で踏み潰してしまう。この痛烈な体験の最中、蛍の死骸は「赤黒い体で、六本腕のある鬼」の幻へと変換される。実佐子が語り、「触覚も取れ、潰れてスイカみたいな匂いがする」と杉本が補強する(こうした転移/逆転移の関係は、臨床的には、より意識化されるべきものだ)蛍の映像は生々しく凄惨だ。そしてそれこそが、「危機」や「解離」といった概念に、肉厚なイメージを与え得るのである。 六本足の蛍は三面六臂の阿修羅像へと重なりつつ巨大化する。その映像は、私達自身にも転移し、異形の生をむさぼり始めてゆくようだ。 |
||
| (こんどう・ひろこ氏=東京女子大学准教授・日本近現代文学・臨床文学専攻) |
||
 |
||
| 「週刊読書人」2009年12月11日号(5面)芸術・文学 |