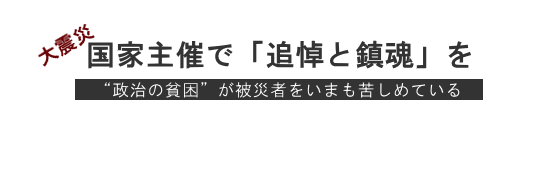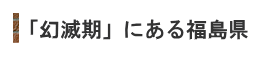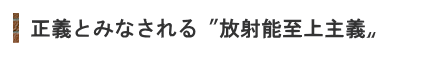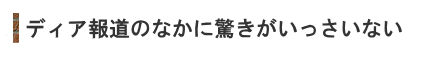|
|
|
|
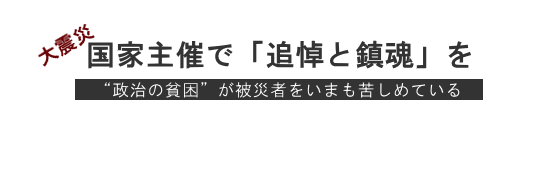 |
|
| |
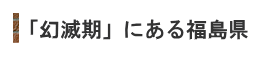 |
|
| |
 先日、福島県須賀川市にあるムシテックワールドに行ってきました。海岸からは50kmほど離れているので津波の被害はありませんでしたが、地震の被害はひどいですね。津波被害にくらべ、地震被害はそれほどメディアで報道されてはいませんが、復旧にはそうとう時間がかかるでしょう。 先日、福島県須賀川市にあるムシテックワールドに行ってきました。海岸からは50kmほど離れているので津波の被害はありませんでしたが、地震の被害はひどいですね。津波被害にくらべ、地震被害はそれほどメディアで報道されてはいませんが、復旧にはそうとう時間がかかるでしょう。 |
|
| |
 そうですね。須賀川あたりは墓地だって二年くらいかかるかと思います。ところで、災害心理学という学問では、大災害のあとの人の心の変化を四段階に分類します。災害直後は「英雄期」といわれ、多くの人が周囲の人々の命や財産を守るために勇気ある行動をとる。この時期は長くは続かず、次の「蜜月期」に入ります。人びとが連帯して困難に耐え、力を合わせて苦情を乗り切ろうという時期で、通常、一週間から最大六ヵ月ほど続くそうです。それが終わると「幻滅期」。いま福島県は、この「幻滅期」にあるという感じがします。個人個人で助け合って何とかなるという時期は、すでに終わってしまった。行政が大胆な支援をしないと、どうしようもない状態です。 そうですね。須賀川あたりは墓地だって二年くらいかかるかと思います。ところで、災害心理学という学問では、大災害のあとの人の心の変化を四段階に分類します。災害直後は「英雄期」といわれ、多くの人が周囲の人々の命や財産を守るために勇気ある行動をとる。この時期は長くは続かず、次の「蜜月期」に入ります。人びとが連帯して困難に耐え、力を合わせて苦情を乗り切ろうという時期で、通常、一週間から最大六ヵ月ほど続くそうです。それが終わると「幻滅期」。いま福島県は、この「幻滅期」にあるという感じがします。個人個人で助け合って何とかなるという時期は、すでに終わってしまった。行政が大胆な支援をしないと、どうしようもない状態です。
たとえば、津波被害のない飯舘村が放射能被害で計画的避難区域に指定され、住民は家を離れています。避難住民を支えているのは、「いつか家に戻る」という思いです。しかし一方、誰もが心のなかに「本当に戻れるのだろうか」という不安を抱いている。この気持ちを圧し殺して頑張っているのです。住民の気持ちからすれば、両方の気持ちに対する解決策がほしい。「戻る」ことに対しては徹底的な除染、「戻れない」場合に対しては、町や村など行政単位がまるごと移転できるような代替地を、国有地などを使って用意することです。この二つは矛盾していますが、住民の気持ち自体が矛盾しているので、両方せざるをえないはずです。 |
|
| |
 福島に赴いて驚いたのは、「うちは〇.二ですから大丈夫」という会話が普通に飛び交っていたことです。県外の人間には何のことだかわからないでしょう。これは放射線量のことです。つまり、年間被曝限度の国際基準が一ミリシーベルトですが、「わが家周辺は〇.二マイクロシーベルトだから大丈夫」ということです。このような会話が日常であることは、やはりおかしいのです。徹底的な除染は必要でしょうね。 福島に赴いて驚いたのは、「うちは〇.二ですから大丈夫」という会話が普通に飛び交っていたことです。県外の人間には何のことだかわからないでしょう。これは放射線量のことです。つまり、年間被曝限度の国際基準が一ミリシーベルトですが、「わが家周辺は〇.二マイクロシーベルトだから大丈夫」ということです。このような会話が日常であることは、やはりおかしいのです。徹底的な除染は必要でしょうね。 |
|
| |
 私は復興構想会議委員を務めたのですが、会議に出席していた委員の方々は、それぞれに「こうすべき」というビジョンを提言し、会議の場では概ね合意に達しました。しかし、それが次に「実行案に移される」といって各省庁を巡っていく。一つの事柄に対して複数の省庁が関係することも多く、巡っているあいだに、何かが〝脱落〟してしまって、「それはないだろう」という思いも何度か体験しました。 私は復興構想会議委員を務めたのですが、会議に出席していた委員の方々は、それぞれに「こうすべき」というビジョンを提言し、会議の場では概ね合意に達しました。しかし、それが次に「実行案に移される」といって各省庁を巡っていく。一つの事柄に対して複数の省庁が関係することも多く、巡っているあいだに、何かが〝脱落〟してしまって、「それはないだろう」という思いも何度か体験しました。
会議では、官僚たちは委員の後ろにずらっと並んでいたのですが、発言はいっさいしません。あとから変更を加えられるくらいなら、その場で発言してもらいたいと思いましたが、そうなると収捨がつかなくなるのでしょう。提言したものが、いろいろな形で実行されるような、されないような、じつに奇妙な感じです。 |
|
| |
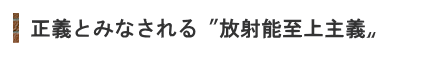 |
|
| |
 それから、やはり菅政権時の民主党は、組織がうまく機能していなかったと思います。海江田元経産大臣の泣きたい気持ちもわからないではない(笑)。少なくとも、非常時の体制ではありませんでしたね。 それから、やはり菅政権時の民主党は、組織がうまく機能していなかったと思います。海江田元経産大臣の泣きたい気持ちもわからないではない(笑)。少なくとも、非常時の体制ではありませんでしたね。 |
|
| |
 日本の組織が機能的でないことは、私は感覚的に知っています。大学がそうでしたから。「大学は何をするところか」といった原点に立ち戻った議論すら、できない。官僚組織という一種のフィルターにかかると、重要な論点が通り抜けてこず、通り抜けてきたものは役に立たないものばかりです。 日本の組織が機能的でないことは、私は感覚的に知っています。大学がそうでしたから。「大学は何をするところか」といった原点に立ち戻った議論すら、できない。官僚組織という一種のフィルターにかかると、重要な論点が通り抜けてこず、通り抜けてきたものは役に立たないものばかりです。
戦争を研究している人は、このことをよく知ってますよ。日本の軍隊が、機能しているようで滅茶苦茶だった。これは日本人の一つの性なのでしょうか。たとえば山本七平さんが『ある異常体験者の偏見』に捕虜収容所の話を書いています。アングロサクソンが捕虜になって収容所に入ると、たちまち機能的な組織ができ、機能的に動く。しかし日本人の場合、まさに「暁に祈る」事件のように、宛名主ができて暴力支配が起こるのです。もちろん、捕虜収容所や刑務所というのは特殊なケースですが、日本人とアングロサクソンではっきり差が出るところが興味深いですね。 |
|
| |
 今回の震災における避難所では、むろんそれとは違って当然なわけですが、自然と自治が生まれてきたようですね。しかもリーダーの発生は、避難所にくる前の社会的地位によってではありません。たとえば、被災地が遠隔されて食料も何も入ってこないという状態で、自ずと誰かが「現在お宅に米がどのくらいありますか」と聞いて回り、それを合計し、家族構成に合わせた配分を計算して配る。このような人が、リーダーになっていきましたね。 今回の震災における避難所では、むろんそれとは違って当然なわけですが、自然と自治が生まれてきたようですね。しかもリーダーの発生は、避難所にくる前の社会的地位によってではありません。たとえば、被災地が遠隔されて食料も何も入ってこないという状態で、自ずと誰かが「現在お宅に米がどのくらいありますか」と聞いて回り、それを合計し、家族構成に合わせた配分を計算して配る。このような人が、リーダーになっていきましたね。 |
|
| |
 避難所であれば、避難者は隣近所の方々で、いってみれば平和的な状況です。もちろん災害は、誰のせいでもありません。お互いに合意もとりやすいので、機能的に動くのでしょう。 避難所であれば、避難者は隣近所の方々で、いってみれば平和的な状況です。もちろん災害は、誰のせいでもありません。お互いに合意もとりやすいので、機能的に動くのでしょう。
在るものをどのように発掘し、配分するかということは、危機的状況では非常に重要なことです。そのときに困るのが、イデオロギーを振り回されることです。 |
|
| |
 ええ、前々から反原発を標榜していた方々は、今回の原発事故に対しても非常にイデオロギー的で、対応するのが大変です。たとえば、深夜二時に電話がかかってきたり、アポなしで急にうちのお寺に訪ねてこられて、とうとうと原発反対を説かれたりする。 ええ、前々から反原発を標榜していた方々は、今回の原発事故に対しても非常にイデオロギー的で、対応するのが大変です。たとえば、深夜二時に電話がかかってきたり、アポなしで急にうちのお寺に訪ねてこられて、とうとうと原発反対を説かれたりする。
また、象徴的なのは子供に対する考え方です。「とにかく福島県に子供を置いていてはいけない」と県外に避難させようとするのですが、このような運動をしている方は、ほとんどが県外の人です。県内にいると、そういった単純な気持ちにはなりません。家族で県外に避難しようとしたとき、子供に「同じクラスの子はここにいるのに、どうして?」と訊かれて、なぜ友達は残らなければならなくて、自分たちは逃げるのか、子供に納得のいく説明ができる親は、ほとんどいないでしょう。そこで無理に連れていくと、子供は「友達のあの子を置いて自分だけ逃げている」ことに、ものすごいストレスを感じてしまう。仮に避難先でいじめにでも遭おうものなら決定的です。避難したほうが猛烈なストレスを受ける場合だってあるわけです。
イデオロギーだけで避難を呼びかける方は、これを複雑な、問題と考えず、ただただ「とにかく放射線量が高いから逃げるべき」という。同じ福島県内で放射線量が高い地域から低い地域へと、細かく子供を移動させようという運動まで始まっています。いったいどこまで動かせば気が済むのでしょうか。放射能至上主義のようになってしまい、コミュニテイーや家族を分断することの重大性を度外視しています。しかも、いまその人たちがすっかり「正義」だとみなされている。
微量の放射線についての危険性は、はっきりいってわかっていません。さらにいえば、わからないと思わないといられない。「わからない」ということが、私らに必要な考え方なのです。そこのところを理解しない外の人たちが強硬にいってくることは、いま、とても暴力的だと感じます。 |
|
| |
 |
|
| |
 放射能というものは、目に見えない、つまり感覚では捉えられないものの典型です。このような抽象的なものを、はたして人間がコントロールできるのかは疑問ですね。原発も同じで、建物の壁はただのコンクリートで、装飾らしいものはほとんどない。理屈という抽象的なものだけでつくられた、いわば「左脳の産物」です。人間には、左脳と右脳があって、文明が進むときは必ず技術と文化が同時に進化します。それはいってみれば、左脳と右脳のバランスをとっているわけです。 放射能というものは、目に見えない、つまり感覚では捉えられないものの典型です。このような抽象的なものを、はたして人間がコントロールできるのかは疑問ですね。原発も同じで、建物の壁はただのコンクリートで、装飾らしいものはほとんどない。理屈という抽象的なものだけでつくられた、いわば「左脳の産物」です。人間には、左脳と右脳があって、文明が進むときは必ず技術と文化が同時に進化します。それはいってみれば、左脳と右脳のバランスをとっているわけです。 |
|
| |
 左脳は理性を、右脳は絵画や音楽などの芸術面、また空間認識も司るといわれますね。 左脳は理性を、右脳は絵画や音楽などの芸術面、また空間認識も司るといわれますね。 |
|
| |
 ええ、仮に左脳しか働かない場合、どのようなことが起こるか。たとえば、「あるものを徹底的に無視」するのです。脳卒中などで右脳が機能しなくなった患者をみると、「半側無視」というケースがあります。見えていないわけではないのに、片側の視野が失われてしまう。だからたとえば、食事のときに右側にあるおかずしか食べなかったり、時計を描かせると、ゼロから十二までの数字を、円の右半分にきれいに納めてしまったりする。左が「根源的になくなってしまう」のです。私は、原発も何かが「根本的に抜け落ちている」気がしてなりません。 ええ、仮に左脳しか働かない場合、どのようなことが起こるか。たとえば、「あるものを徹底的に無視」するのです。脳卒中などで右脳が機能しなくなった患者をみると、「半側無視」というケースがあります。見えていないわけではないのに、片側の視野が失われてしまう。だからたとえば、食事のときに右側にあるおかずしか食べなかったり、時計を描かせると、ゼロから十二までの数字を、円の右半分にきれいに納めてしまったりする。左が「根源的になくなってしまう」のです。私は、原発も何かが「根本的に抜け落ちている」気がしてなりません。 |
|
| |
 かつて炭抗節というものがありましたが、これは右脳を使って恐怖心を紛わしつつ、同時にプライドや仲間意識も形成していた気がします。ですが、原発は恐怖心の性質が違う。「家族を養っていくためには何ミリシーベルト被曝している」というのは、プライドにならないでしょうね。 かつて炭抗節というものがありましたが、これは右脳を使って恐怖心を紛わしつつ、同時にプライドや仲間意識も形成していた気がします。ですが、原発は恐怖心の性質が違う。「家族を養っていくためには何ミリシーベルト被曝している」というのは、プライドにならないでしょうね。 |
|
| |
 さらに重要なのは、原発は「維持しなければならない」ものだということです。しかし、これほど抽象的なものを、はたして長期的に存続させることが可能なのか。宇宙ロケットのように、いっぺん飛ばして終わりというものだったらまだしも、原発のように常時運転しなければならないものが人間の本性と合っているのか、はなはだ疑問です。それを上手に続けていくのは、けっこうな大問題であって、お寺の制度などもそうだと思いますけれど、特別な人でなければ維持できないなら、長年は無理ですよね。 さらに重要なのは、原発は「維持しなければならない」ものだということです。しかし、これほど抽象的なものを、はたして長期的に存続させることが可能なのか。宇宙ロケットのように、いっぺん飛ばして終わりというものだったらまだしも、原発のように常時運転しなければならないものが人間の本性と合っているのか、はなはだ疑問です。それを上手に続けていくのは、けっこうな大問題であって、お寺の制度などもそうだと思いますけれど、特別な人でなければ維持できないなら、長年は無理ですよね。 |
|
| |
 ええ、お寺はシステムが安定しているので、普通の私でも大丈夫です。(笑) ええ、お寺はシステムが安定しているので、普通の私でも大丈夫です。(笑) |
|
| |
 だいたい、放射能がどれほど危険か、さっぱりわからない。東海村の臨界事故のように、大量の放射能を一気に浴びると急性放射性障害が起きます。しかし、微量の放射能については、先ほどご指摘のようにわかりません。放射能自体は目に見えないし、周囲にいる人たちの顔色が悪くなるということもない。そこでガイガ―カウンターを使うのでしょうが、あれってインチキされたらどうするんですか。自分が気に食わない人間にはできるだけ鈍い線量計を付けるなどといったテロの可能性だっていくらでもある。そういう用心を全部しなければならないとすると、それは度を越しています。 だいたい、放射能がどれほど危険か、さっぱりわからない。東海村の臨界事故のように、大量の放射能を一気に浴びると急性放射性障害が起きます。しかし、微量の放射能については、先ほどご指摘のようにわかりません。放射能自体は目に見えないし、周囲にいる人たちの顔色が悪くなるということもない。そこでガイガ―カウンターを使うのでしょうが、あれってインチキされたらどうするんですか。自分が気に食わない人間にはできるだけ鈍い線量計を付けるなどといったテロの可能性だっていくらでもある。そういう用心を全部しなければならないとすると、それは度を越しています。 |
|
| |
 今年の福島の桃は、これまでにないというくらい、ものすごくおいしいものでした。農家の方はセシウムが入らないようにかなり努力しましたけども、仮に含んでいたとしても、おいしさは変わりません。ところが、この「おいしい」と思う感覚に対して、まさに左脳がブレーキをかけます。実感はないけれども、何ベクレルだから食べるな、というわけです。これはやはり不健全ですよ。 今年の福島の桃は、これまでにないというくらい、ものすごくおいしいものでした。農家の方はセシウムが入らないようにかなり努力しましたけども、仮に含んでいたとしても、おいしさは変わりません。ところが、この「おいしい」と思う感覚に対して、まさに左脳がブレーキをかけます。実感はないけれども、何ベクレルだから食べるな、というわけです。これはやはり不健全ですよ。
|
|
| |
 現代人は、世界を論理的に把握できる、少なくとも把握できるという前提でいる。社会全体が「佐脳化」しているのです。 しかし、その考え方はとても危ない。いつの時代も人間が宗教に関心をもつのは、人間の行なうことに対する自然の防護装置になっているのでしょう。ときどきは人間自身がどの程度のものかということに立ち戻らなければやっていけません。 現代人は、世界を論理的に把握できる、少なくとも把握できるという前提でいる。社会全体が「佐脳化」しているのです。 しかし、その考え方はとても危ない。いつの時代も人間が宗教に関心をもつのは、人間の行なうことに対する自然の防護装置になっているのでしょう。ときどきは人間自身がどの程度のものかということに立ち戻らなければやっていけません。
先ほどいったように、原発そのものが完全に左脳でコントロールしなければならないもので、コストや安全性もすべて頭で考えて動かさなければいけないものだったわけです。これには、非常に優秀な人材が必要です。いちばん最初に原発を推進した人たちは、たしかに優秀だった。当時、秀才といわれる人間はみな物理学を専攻したものです。そのような創業時の人たちが目を光らせている時期はきちんと動くかもしれない。ところが現状までに原発が増えてしまうと、作業がルーティン化し、平均的な人間が動かすようになります。原発を、はたして平均値で動かせるのか。そのことを関係者が本気で考えていなかったのに、気づかなかった。つまり、原発に対して本気で考えていなかったのです。 |
|
| |
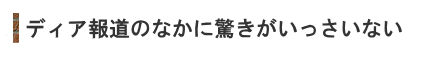 |
|
| |
 放射線量が百ミリシーベルト以上になると、被曝量に比例して発がん率が上がります。しかし百ミリシーベルト以下については、はっきりいってわかっていません。悲観派は、百ミリシーベルト以下の発がん率も直線的に考えるべきだという。一方で楽観派は、自然のなかにも放射線はいくらでも存在しているし、発がん率が高まるかわからないという。いずれにしても証拠がないので、「信じるか信じないか」になってしまいます。これは、ある種の新興宗教のようでもあります。 放射線量が百ミリシーベルト以上になると、被曝量に比例して発がん率が上がります。しかし百ミリシーベルト以下については、はっきりいってわかっていません。悲観派は、百ミリシーベルト以下の発がん率も直線的に考えるべきだという。一方で楽観派は、自然のなかにも放射線はいくらでも存在しているし、発がん率が高まるかわからないという。いずれにしても証拠がないので、「信じるか信じないか」になってしまいます。これは、ある種の新興宗教のようでもあります。 |
|
| |
 仮に放射能の危険性が直線的に続いているとしても 、値が小さくなるにつれて危険性が小さくなります。すると、ほかの危険性との秤になる。つまり、その小さな危険性と、東京で交通事故に遭う危険性と、どちらが高いか、という話になります。 仮に放射能の危険性が直線的に続いているとしても 、値が小さくなるにつれて危険性が小さくなります。すると、ほかの危険性との秤になる。つまり、その小さな危険性と、東京で交通事故に遭う危険性と、どちらが高いか、という話になります。
ですが、このような統計や確率といったものは、じつは個人にはまったく関係ない。「千人のうち一人が交通事故に遭います」といわれても、「自分は事故に遭わない」と考えるのが普通でしょう。自分が生きているということは、絶えずゼロか百かの「賭け」率をできるだけよくしていこうと思っているのでしょうが、それは完全に左脳の働きで、実際の現実とは、ほとんど関係がないのです。たとえば、禁煙して、ジョギングして、ダイエットして、サプリメントを摂って、交通事故などの不測の事態で亡くなった人が何人いたことか。
理屈に偏っていくと、大穴があいていても、本人がまったく気づかないということが起こるのです。それを「医者の不養生」「紺屋の白袴」という。今回の原発事故も、そのような穴におちたのでしょう。 |
|
| |
 東京電力にも妙な体質ができあがってしまいましたね。たとえば、より安全な型の原子炉が開発されたといっても「では、それに替えよう」という発想にならず、とにかく「現在の安全性が崩れるようなことはない」と固執して、本当に〝神話〟になってしまっていた。 東京電力にも妙な体質ができあがってしまいましたね。たとえば、より安全な型の原子炉が開発されたといっても「では、それに替えよう」という発想にならず、とにかく「現在の安全性が崩れるようなことはない」と固執して、本当に〝神話〟になってしまっていた。 |
|
| |
 左脳は「こだわる」という性質ももっているのです。たとえば夜道に光るものが一つあったときに「あれはヘビの目だ」と考えたとする。しかしよく見ると光が一つしかない。それでも、一度ヘビだと思うと、ついつい「これは片目のヘビだ」と考えてしまう(笑)。議論は理性でするものだと思っているので、「片目のヘビ」になりやすい。原発も、「危ないかもしれない。ではどうするか」とはならず、逆に固執したのです。 左脳は「こだわる」という性質ももっているのです。たとえば夜道に光るものが一つあったときに「あれはヘビの目だ」と考えたとする。しかしよく見ると光が一つしかない。それでも、一度ヘビだと思うと、ついつい「これは片目のヘビだ」と考えてしまう(笑)。議論は理性でするものだと思っているので、「片目のヘビ」になりやすい。原発も、「危ないかもしれない。ではどうするか」とはならず、逆に固執したのです。 |
|
| |
 メディアに対しても不信感があります。たとえば、岩手県一関市の稲わらから高濃度の放射線の値が出たといったとき、新聞などの報道のなかに、驚きがいっさいなかった。いままで彼らが行なってきた報道からすれば、一関から高い値が出たということは予想外の事態のはずです。しかし「なぜこの場所から!?」と疑問を感じている様子もないし、原因を追及するわけでもない。同じように岩手県陸前高田市の松から放射性物質が検出されたことについても、新聞やテレビは事実を淡々と述べていただけです。 メディアに対しても不信感があります。たとえば、岩手県一関市の稲わらから高濃度の放射線の値が出たといったとき、新聞などの報道のなかに、驚きがいっさいなかった。いままで彼らが行なってきた報道からすれば、一関から高い値が出たということは予想外の事態のはずです。しかし「なぜこの場所から!?」と疑問を感じている様子もないし、原因を追及するわけでもない。同じように岩手県陸前高田市の松から放射性物質が検出されたことについても、新聞やテレビは事実を淡々と述べていただけです。 |
|
| |
 上杉隆さんが『Voice』で書いていますよ。彼らは知っていて、報じないのだと(笑)。メディアが事実を報道しないのは、原発の対立関係の話にどこか根本的に通じるものがあります。原発の安全を主張する人は「絶対安全」、危険を主張する人は「絶対危険」。実際はどうなのか、というところが抜けている。これも日本人の特性でしょう。アングロサクソンは、まず事実を重視します。そして事実の前には、賛成派も反対派も自らの主張を抑制する。日本人はそれが苦手ですね。データが出るまで待ってくれというべきところを、すぐ結論を求めてしまう。 上杉隆さんが『Voice』で書いていますよ。彼らは知っていて、報じないのだと(笑)。メディアが事実を報道しないのは、原発の対立関係の話にどこか根本的に通じるものがあります。原発の安全を主張する人は「絶対安全」、危険を主張する人は「絶対危険」。実際はどうなのか、というところが抜けている。これも日本人の特性でしょう。アングロサクソンは、まず事実を重視します。そして事実の前には、賛成派も反対派も自らの主張を抑制する。日本人はそれが苦手ですね。データが出るまで待ってくれというべきところを、すぐ結論を求めてしまう。 |
|
| |
 原発がここまで増えたのは、やはり国策だったことが大きいですね。私は一九五六年生まれですが、そのころから原子力政策が始まり、私が中学生のときに福島第一原発ができました。ちょうど大阪万博があったころで、経済は右肩上がりという時代です。私が子供のころ、毎週火曜の六時十五分といえば『鉄腕アトム』の時間です。主人公アトムの兄弟は、妹のウランちゃんとコバルト兄さん、といったように、あの時代は原発が間違いなく明るい未来として描かれていました。 原発がここまで増えたのは、やはり国策だったことが大きいですね。私は一九五六年生まれですが、そのころから原子力政策が始まり、私が中学生のときに福島第一原発ができました。ちょうど大阪万博があったころで、経済は右肩上がりという時代です。私が子供のころ、毎週火曜の六時十五分といえば『鉄腕アトム』の時間です。主人公アトムの兄弟は、妹のウランちゃんとコバルト兄さん、といったように、あの時代は原発が間違いなく明るい未来として描かれていました。 |
|
| |
 技術に対する見方が楽観的でしたね。ちょうどそのころは、大学のなかでも生物についてDNAの構造解析ができるようになりました。つまり、理屈で生物がわかると考え始めていたのです。もちろんそれは錯覚なのですが、技術に対する希望が強くありました。宇宙ロケットも。あんなものはおかしいといっているのは私ぐらいなもので(笑)、あれよあれよという間に物事が進んでいったという感じでした。 技術に対する見方が楽観的でしたね。ちょうどそのころは、大学のなかでも生物についてDNAの構造解析ができるようになりました。つまり、理屈で生物がわかると考え始めていたのです。もちろんそれは錯覚なのですが、技術に対する希望が強くありました。宇宙ロケットも。あんなものはおかしいといっているのは私ぐらいなもので(笑)、あれよあれよという間に物事が進んでいったという感じでした。 |
|
| |
 それに、ある程度の年齢の方たちは、原発を誘致してきた歴史を知っています。周辺地域では東電に勤めている人もいますし、電源三法交付金の恩恵も受けていますから、反対を叫んでは悪いだろうという感覚もあったはずです。たしかにそれは、ある意味ではまっとうな恥じらいだともいえるのですが。 それに、ある程度の年齢の方たちは、原発を誘致してきた歴史を知っています。周辺地域では東電に勤めている人もいますし、電源三法交付金の恩恵も受けていますから、反対を叫んでは悪いだろうという感覚もあったはずです。たしかにそれは、ある意味ではまっとうな恥じらいだともいえるのですが。 |
|
| |
 高橋秀実さんが『からくり民主主義』で、原発と米軍基地は構造が同じだと書いています。住民は賛成と反対が拮抗し、わずかに賛成が上回る程度が望ましい、それがもっともお金をもらえるのだ、と。また原発周辺の市町村は、平成の大合併で合併していないところばかり。要するに分割統治です。住民が少なければ少ないほど、地元の意見が統一しやすいですから。 高橋秀実さんが『からくり民主主義』で、原発と米軍基地は構造が同じだと書いています。住民は賛成と反対が拮抗し、わずかに賛成が上回る程度が望ましい、それがもっともお金をもらえるのだ、と。また原発周辺の市町村は、平成の大合併で合併していないところばかり。要するに分割統治です。住民が少なければ少ないほど、地元の意見が統一しやすいですから。 |
|
| |
 |
|
| |
 今回の原発事故では、三カ月ぐらいには対策の議論が出尽くしているのですが、その後まったく進展しません。「放射能を徹底的に除染する」という言葉は出てくるのですが、では山林はどうするんですか、と問うても誰も答えられない。「自衛隊を入れます」という国会議員もいますが、いつどこに入れるのかもわからない。とにかく動きが鈍いことが、住民のいちばんのストレスです。やはり、政治の貧困を感じますね。 今回の原発事故では、三カ月ぐらいには対策の議論が出尽くしているのですが、その後まったく進展しません。「放射能を徹底的に除染する」という言葉は出てくるのですが、では山林はどうするんですか、と問うても誰も答えられない。「自衛隊を入れます」という国会議員もいますが、いつどこに入れるのかもわからない。とにかく動きが鈍いことが、住民のいちばんのストレスです。やはり、政治の貧困を感じますね。
住民のストレスということでいうと、政府はとにかく仮設住宅の建設と入居を急がせましたが、これは表面上、被災者の苦脳を隠しただけです。一時避難所は悲惨さがあまりにもあからさまだったので、東京からきた人たちは目を覆うわけです。それで「一日も早く仮設を」というわけですが、じつは、仮設住宅に入りたくないという被災者が三割ほどもいました。この気持ちは、被災者でない人は想像もつかないでしょう。寝るときは独りのほうがいいですが、被災者は仕事もなくなり、昼間も独りぼっちでいるしかありません。だから昼間は、みなで一緒に過ごしたいのです。だからせめて仮設住宅から通えるところに、みんなで集まってご飯を食べれるような場所だけは残してほしいと訴えたのですが、どうもダメなのです。そういう前例がないのでしょう。
また今回の事態を受けて、被害に遭った土地に再び住むのは危険だから高台に住みましょう、という大原則が掲げられました。ですが、なかなかうまく事は進みません。漁師が海の近くを離れられるものか、と元の土地に住んでしまうケースも、すでに出ています。そう考えると、高台移住というのは非現実的でしょう。 |
|
| |
 結局は元の場所に住むんですよ。本誌九月号の巻末「平成始末」に山折哲雄さんが、「安全な場所なんか無い」と言う話を書いておられますが、危険なところに住むなといいはじめたら、そもそも日本列島に住むのがおかしいということになる。世界中見渡しても、こんな危ないところはないのですから。人間も動物ですから、逃げればいい。私たちの世代は、子供のときは戦災でしたから、逃げるのには慣れています。 結局は元の場所に住むんですよ。本誌九月号の巻末「平成始末」に山折哲雄さんが、「安全な場所なんか無い」と言う話を書いておられますが、危険なところに住むなといいはじめたら、そもそも日本列島に住むのがおかしいということになる。世界中見渡しても、こんな危ないところはないのですから。人間も動物ですから、逃げればいい。私たちの世代は、子供のときは戦災でしたから、逃げるのには慣れています。 |
|
| |
 最近は「追いかける」ばかりですからね 最近は「追いかける」ばかりですからね |
|
| |
 歴史とくに西洋史においては天災を無視しがちです。しかし、自然条件が歴史に与える影響はじつは大きい。たとえば有名な話では、フランス革命は、日本の天明の大飢饉と同時期に起きている。 歴史とくに西洋史においては天災を無視しがちです。しかし、自然条件が歴史に与える影響はじつは大きい。たとえば有名な話では、フランス革命は、日本の天明の大飢饉と同時期に起きている。 |
|
| |
 火山噴火で火山灰が舞い上がり、世界的な冷害が訪れたといわれます。さらに西洋でも東洋でも、ペストなどの疫病が大きな影響を及ぼしていますね。 火山噴火で火山灰が舞い上がり、世界的な冷害が訪れたといわれます。さらに西洋でも東洋でも、ペストなどの疫病が大きな影響を及ぼしていますね。 |
|
| |
 現代のマスコミも、首相がどうのこうのといいますが、時代が変わるときは物理的な要因のほうが大きいのです。人間のそれまでの感受性が一致するほどの局面さえあるのですから。 現代のマスコミも、首相がどうのこうのといいますが、時代が変わるときは物理的な要因のほうが大きいのです。人間のそれまでの感受性が一致するほどの局面さえあるのですから。 |
|
| |
 鴨長明が晩年住んだような家なら、可動式で組み立て式ですから、まだしも天災に見舞われてもショックは少ないのでしょうが。でも可動式のはずが、五年移動しないうちに、土台にコケが生えたとか。 鴨長明が晩年住んだような家なら、可動式で組み立て式ですから、まだしも天災に見舞われてもショックは少ないのでしょうが。でも可動式のはずが、五年移動しないうちに、土台にコケが生えたとか。 |
|
| |
 それが日本なのです。私だったら性懲りもなく、また同じところに住むでしょうね。人間は性懲りもないものですが、それは一つの健康な思考だと思います。 それが日本なのです。私だったら性懲りもなく、また同じところに住むでしょうね。人間は性懲りもないものですが、それは一つの健康な思考だと思います。 |
|
| |
 そうですね。ここまでの目に遭うと、土地に対する執着が弱ければ移動しようと思うのかもしれませんが、私の場合も、歴史とともに歩んできた寺でもありますので、移動はできないですよね。 そうですね。ここまでの目に遭うと、土地に対する執着が弱ければ移動しようと思うのかもしれませんが、私の場合も、歴史とともに歩んできた寺でもありますので、移動はできないですよね。 |
|
| |
|
|
| |
 最近、日本は改元をしてはどうかと思っているのです。これだけ国を揺るがす大災害に見舞われたのですから。 最近、日本は改元をしてはどうかと思っているのです。これだけ国を揺るがす大災害に見舞われたのですから。 |
|
| |
 私もそう感がています。また慰霊も考えなくてはいけませんね。あるところで目処をつけないと、この国はいわば、怪我をしたままの状況が続いてしまいます。何かをしたからといって元に戻るというわけではありませんが、切り替えるタイミングが必要です。 私もそう感がています。また慰霊も考えなくてはいけませんね。あるところで目処をつけないと、この国はいわば、怪我をしたままの状況が続いてしまいます。何かをしたからといって元に戻るというわけではありませんが、切り替えるタイミングが必要です。
知り合いが、LED電球を内部に入れた一輪挿しの花瓶のようなものを間伐材の台に立て、写真を貼ったり名前を書けるようにした簡易の仏壇をつくったのですが、これに注文が大量にくるそうです。避難所でも仮設住宅でも、仏壇を置いている人はまずいない。つまりいま、慰霊をしたくてもする場所がないのです。 |
|
| |
 神社庁や各宗派の本山も、簡易神棚や仏壇を配りはじめましたが、行き渡っていませんね。 神社庁や各宗派の本山も、簡易神棚や仏壇を配りはじめましたが、行き渡っていませんね。
ところで今年、お盆を迎えるにあたって、多くの被災者は迷いました。また家族のご遺体が見つかっていない方が大勢います。「遺体が見つからない以上、希望は捨てない。だけど、このまま何もせずにお盆を過ごしていいのだろうか」と。お盆は死者供養の行事です。亡くなった方の名前を書いた灯籠を流したり、また名前の書いた札を燃やしたりする。それを行ないたい、と多くの方が思いました。今回の震災をきっかけに、死亡証明はわりと簡単にできるよになったので、家族の遺体は見つかっていなくともとりあえずは死亡したことにして、お盆を迎えたのです。ですが、死亡証明はしても、死亡したときに関係者に支払われる保険や補償の申請はしないという方が多くいらっしゃいました。補償がほしいから死亡申請をするのではない。むしろ、いまの時点で補償申請をすることは、いなくなってしまった人に対する冒涜のように感じてしまう。個人のなかにも葛藤があるわけです。しかし、区切りをつけたいという気持ちも強くあります。
震災で家族を亡くした多くが、まだお葬式を出せていません。つまり、きちんと泣けていないのです。私はお葬式をする側の立場の人間ですが、やはり泣く場をつくってあげることは大切です。いま個人レベルではとてもお葬式をできる状況ではないので、国レベルの慰霊を考えるべきでしょう。 |
|
| |
 泣くとか笑うというのは、かなり複雑で、非常に人間的なものです。結果的に泣いたり笑ったりしているわけで、意識的に泣いたり笑ったりしているわけではない。悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいという面がある。つまり、身体反応が先にあって、あとから「悲しみを悲しみとして」意識するわけです。 泣くとか笑うというのは、かなり複雑で、非常に人間的なものです。結果的に泣いたり笑ったりしているわけで、意識的に泣いたり笑ったりしているわけではない。悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいという面がある。つまり、身体反応が先にあって、あとから「悲しみを悲しみとして」意識するわけです。
逆説的ですが、葬式は生きているという実感をもつ場でもあります。それがカタルシスとなって、いろいろなことが流される。さらに「死んだ相手に対して生きている自分」というコントラストがあって、生きるということに力を与える。そのため、慰霊はどの社会にも必ずあります。それを上手にできることを「まつりごと」というのです。被災地域では個々の事情が違います。だからたしかに、国で行なうのがいいかもしれません。 |
|
| |
 復興構想会議で決定した提言のなかで、冒頭の七原則の第一に「追悼と鎮魂」を入れました。ですが、役所の姿勢は非常に消極的なのです。特定の宗教や宗派を支援するわけではなく、被災に遭ったすべての施設に対して援助してほしいと申し上げたのですが、その文面をどうしても入れてくれなかった。追悼や鎮魂を行なう場である寺や神社が被災しているのに、どうやって追悼と鎮魂をせよというのでしょう。災害の悲惨さを忘れないための「鎮魂の森」やモニュメントを、防災の観点も含めてつくる話は出ましたが、儀式にまつわる話はありませんでした。とても残念です。 復興構想会議で決定した提言のなかで、冒頭の七原則の第一に「追悼と鎮魂」を入れました。ですが、役所の姿勢は非常に消極的なのです。特定の宗教や宗派を支援するわけではなく、被災に遭ったすべての施設に対して援助してほしいと申し上げたのですが、その文面をどうしても入れてくれなかった。追悼や鎮魂を行なう場である寺や神社が被災しているのに、どうやって追悼と鎮魂をせよというのでしょう。災害の悲惨さを忘れないための「鎮魂の森」やモニュメントを、防災の観点も含めてつくる話は出ましたが、儀式にまつわる話はありませんでした。とても残念です。 |
|
| |
 先日、ラオスを飛行機で飛んだのですが、人間が固まって住んでいる場所に、必ずといっていいほど赤い屋根が見えるんですね。全部お寺です。お寺が、集落と共にあるんですね。 先日、ラオスを飛行機で飛んだのですが、人間が固まって住んでいる場所に、必ずといっていいほど赤い屋根が見えるんですね。全部お寺です。お寺が、集落と共にあるんですね。 |
|
| |
 カンボジア難民も、国境を越えて逃げて、みんなで最初のお寺を建て、そこに寝泊まりしながらそれぞれの家を建てていったといいます。お寺がコミュニティーの要になっているんですね。日本の地域ごとにあるお寺や神社も、同じ役割を担っているのです。そのことは忘れてはいけないと思います。 カンボジア難民も、国境を越えて逃げて、みんなで最初のお寺を建て、そこに寝泊まりしながらそれぞれの家を建てていったといいます。お寺がコミュニティーの要になっているんですね。日本の地域ごとにあるお寺や神社も、同じ役割を担っているのです。そのことは忘れてはいけないと思います。
そして、追悼と鎮魂を国で行なうならば、ぜひ皇室の皆さまご臨席で合同追悼式ができれば、と切に願っています。天皇陛下と皇后陛下はじめ皇族の皆さまが震災後、毎週のように被災地を訪問されました。あれだけ悲惨な状況に追いやられた被災者が、そこで初めて笑顔をみせた。陛下が被災地にいらっしゃると、本当に人びとの心が平らかになるのです。 |
|
| |
 中立的ということを考えても、皇室の方々にご臨席いただくのは、とても重要なことですね。来年の三月十一日までに、ぜひ実現すべきだと思います。 中立的ということを考えても、皇室の方々にご臨席いただくのは、とても重要なことですね。来年の三月十一日までに、ぜひ実現すべきだと思います。 |
|
| |
|
|
|
「Voice」2011年11月号 |
|
|
|
|
|
|
|