|
|
|
|
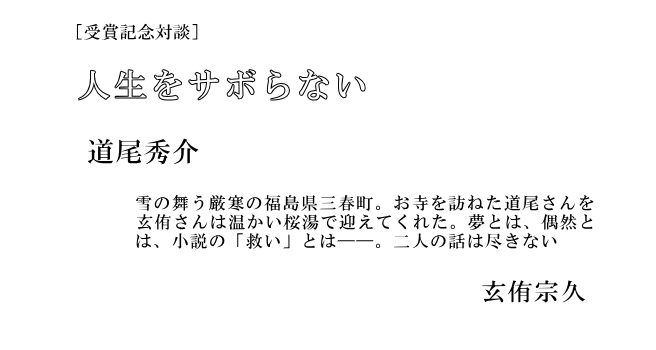 |
|
|
玄侑 受賞、おめでとうございます。
道尾 ありがとうございます。一度玄侑さんのお寺(福島県三春町の福聚寺)に伺いたいと思っていたので、今日はすごく楽しみにしてきたんです。
玄侑 おめでたい席なので、桜湯をお出ししました。どうぞ。
道尾 桜湯ですか、めずらしいですね。いただきます。……あ、おいしい。
玄侑 みなさんから言われるでしょうけど、待ちに待った直木賞ですね。
道尾 はい。まわりの人が喜んでくれるのが、やっぱりうれしいです。
玄侑 私も今朝、寺の入り口の掲示板に一筆、道尾さんのために書きましてね。「不二ふ一 銀 の雪 うるはしき」。「銀 の雪 うるはしき」。「銀 の雪」って言葉、聞いたことあります? 銀のお椀に雪を盛るということなんですけど。 の雪」って言葉、聞いたことあります? 銀のお椀に雪を盛るということなんですけど。
道尾 いえ、ないです。
玄侑 一昨年、『鷺と雪』という作品が直木賞をとったでしょう。
道尾 ええ、北村薫さんの。
玄侑 「銀 の雪」も、「鷺と雪」も、どちらも禅語なんですよ。「鷺 の雪」も、「鷺と雪」も、どちらも禅語なんですよ。「鷺 、雪に 、雪に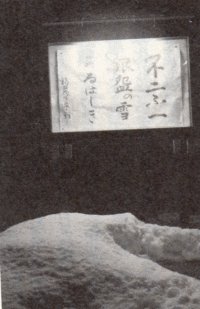 立つ」、鷺が雪の中に立っているということで、「銀 立つ」、鷺が雪の中に立っているということで、「銀 の雪」と意味はほとんど同じなんですけど、要するに、銀のお椀も白鷺もそれ自体が綺麗で、輝いていて、すばらしい。一方、そこに雪が降っても、同じように白銀に輝いて、似たような美しさである。これが「不二」ですね。しかし、一見似てはいても、その美しさの源はやっぱり違う。質の異なる美しさがあるということで、これが「不一」。だから、直木賞をおとりにならなかったとしても、道尾さんの小説は銀椀のように輝いている。けれども、いざそこに雪が盛られてみるとなおさら麗しく見えるということで、やっぱり賞をおとりになってよかったなあと。 の雪」と意味はほとんど同じなんですけど、要するに、銀のお椀も白鷺もそれ自体が綺麗で、輝いていて、すばらしい。一方、そこに雪が降っても、同じように白銀に輝いて、似たような美しさである。これが「不二」ですね。しかし、一見似てはいても、その美しさの源はやっぱり違う。質の異なる美しさがあるということで、これが「不一」。だから、直木賞をおとりにならなかったとしても、道尾さんの小説は銀椀のように輝いている。けれども、いざそこに雪が盛られてみるとなおさら麗しく見えるということで、やっぱり賞をおとりになってよかったなあと。
道尾 ありがとうございます。この対談が終わったら、じっくり拝見して帰ります。
玄侑 これまでも四回連続で候補になっていたわけですけれど、今回の『月と蟹』ほど、賞をとるべきだよなあ、とってほしいなあ、と願ったことはありませんでした。やっぱり、作品のクオリティが、ひときわすばらしかった。
道尾 最新刊でそう言ってもらえると、すごくうれしいです。
玄侑 もちろん単純には一作ごとのクオリティが比較できないくらい、道尾さんの小説はバラエティに富んでるんですが、初期にはもっとミステリーっぽいものをお書きになってましたよね。ミステリーをお書きになっても謎解きそれ自体が目的ではないんだけど、かねてからおっしゃっていたけれども。
道尾 ええ。ミステリーの仕掛けは、感情やテーマを伝えるための手段としてとても効果的だと思っていたんです。
玄侑 ただ、ミステリーのロジックって、パタパタパタッと見事に決まっても、読んでいるときには感心するけれど、後々まで残らないんですよね。そういう意味では、たとえば『シャドウ』に出てくる凰介と亜紀、あの二人も『月と蟹』の慎一と同じ小学五年生なんです。『シャドウ』は私が初めて読んだ道尾さんの小説で、とても面白いミステリーなんですが、後半、主人公の二人にやや説明させすぎているんじゃないかという気がした。そのために、彼らの感情の印象が弱くなってしまっている憾みがあるんですね。そういう初期作品に比べると、このところ道尾さんの感情を描き出す筆力はぐんぐん上がっていて、ことに『月と蟹』は慎一たちの思いが、読語、いつまでも心に残りますね。鮮烈な記憶、感情を喚起させるというんでしょうか。二人の少年と少女が出会う、その情景を、距離をとって外から描くのではなくて、あたかも自分自身が少年時代に戻ったかのように読ませてくれて、これは大変な文学的達成だと思いました。
道尾 ありがとうございます。『シャドウ』の頃はまだストーリーが先にあって、物語が人物を動かしているところがあったんですね。でも、『月と蟹』の場合は、慎一たち三人が勝手に物語をつくっていてくれて、作者の僕はただそれを文章化しているだけ、という感覚が常にありました。
玄侑 前にも話したことがあると思いますけど、少年小説といえば私、北杜夫さんの『幽霊』が大好きなんです。でも、道尾さんの『月と蟹』を読んで、まったく別の意味で新しい少年文学をお作りになったなあ、新たな少年小説が誕生したなあ、という気がしました。物語の背後に作者がいるという感覚があって、読んでいて安心感につながることもあるんですが、『月と蟹』では道尾さん自身は完全に黒衣に徹していて、それが読む人を少年そのものにしてしまうんでしょうね。
道尾 そこはいちばん気を遣ったところなので、玄侑さんの感想を伺ったとき、本当はにほっとしたんです。小学五年生の言葉ってたとえばカギカッコの中の台詞ならいくらでもそれらしく書けるんですけど、地の文を書くのがすごく難しいんですよ。五年生の男の子が知っている語彙だけで書いたら小説にならないですし、かといって難しい言葉で使いすぎたら、大人の回想譚になってしまう。回想の形で書かれたもっと美しい少年小説が『幽霊』だと思うので、もしその方向で書いていたら、『幽霊』の二番煎じになってしまっていただろう、とも思いました。
|
|
| |
|
|
| |
流されないバンカラ魂 |
|
| |
|
|
| |
玄侑 道尾さんが私の講演会に来てくださったのが、最初にお目にかかったきっかけですね。
道尾 そうです。今からちょうど三年前の一月、池袋コミュニティ・カレッジの講演会におじゃまして。
玄侑 ええ。会の後のサイン会にも並んでくれて、「ミステリー書いてます」って名刺をくださった。
道尾 その少し前、「日刊ゲンダイ」に玄侑さんの『龍の棲む家』の書評を書かせてもらったんですよ。まだ一面識もなくて、僕が一方的に玄侑さんのファンという立場だったので、あの書評は読んでくれたかな、くれていないかな、なんて思いながら列に並んでサインをもらった覚えがあります。
玄侑 当時、道尾さんはかなりミステリーっぽいミステリーを書いていたでしょう。わざわざ講演会に来てくださるほどの私への興味って、いったい何だったんですか。
道尾 もう単純に、玄侑さんの小説が好きだったんです。現役の僧侶が小説を書いて芥川賞を受賞したというので、玄侑さん、あちこちのメディアに出てらしたじゃないですか。それで興味をもって受賞作の『中陰の花』を読んだら、「自分はどうしてこの人の小説をこれまで読んでなかったんだろう」と、もう一気にファンになっちゃったんです。文章の美しさ、比喩の的確さに夢中になって、すぐにデビュー作の『水の舳先』を読みました。あとはネットで一括注文して、届いた順から全部読ませていただいて。
玄侑 ありがとうございます。私も道尾秀介という作家を知ることができて、よかったなあと思っています。文章の美しさといえば、まさしく道尾さんの小説こそ、書かれるごとにどんどんそれを感じさせるようになってきています。
私が感心したのは、『ソロモンの犬』という作品があるでしょう。
道尾 ええ。
玄侑 道尾さんのユーモアセンスについてはあまり取り沙汰されませんが、あの作品に溢れるおかしさは抜群ですね。青年たちの醸しだす爽やかな感じが、やがて恐ろしい世界へと振れていくあの空気、それを安定的に支えているのが語り手のおかしさだと思いました。これは私には書けないなあ、と思ったものです。『月と蟹』で見せてくれた子供を描く筆致も見事ですけど、若者がまたうまいですね。たとえば、『月の恋人』に出てくる青年社長がいますね。
道尾 葉月蓮介。
玄侑 酷薄で、人と情を交えない人間として描いてるんだけど、作者はだんだん彼をそうではないところへと戻していきますよね。葉月って一見冷たくて嫌なやつなんだけど、じつはけっこう古風なところがあるんだな、とわかってくるんです。線香花火の美しさに心を動かされたり、メロン農家のおじいちゃんに大事なことを学んだり。
道尾 そうですね。
玄侑 私は、それが素朴にうれしかった。道尾さんの描く若者って、どこか情の世界への渇望のようなものを持っているように感じます。渇望しても得られるかどうかわからないけれど、渇望せずにはいられない若者たち。そのへんは意識されていますか。
道尾 う―ん……自分の書くもののことって、なかなか客観的にはわからないんですけど、どんな小説でも、僕が表現したいのは人間の感情なんですね。感情の結実を書くために、いったん感情の欠如や行き違いといったマイナスの部分を書く。順序でいうとそういうことだと思っています。
玄侑 『月と蟹』にもまさにそういう面があって、ある意味では、現代的ではないという言い方もできるかもしれないけど、私たちにしたらものすごくほっとするような、古風な倫理を小説の中に感じることがあります。
道尾 古きよき時代の価値観を書いているということは、自分でも意識しているんです。それこそドラマの『寺内貫太郎一家』のような、強がっている貫太郎の弱さをきんおばあちゃんの演技で語らせたりする。昔ながらの物語のパターンを踏襲しているつもりですね。
玄侑 なるほど、古風で斬新、か。
道尾 それと、小説を書いていて思うのは、ここ最近、ストーリーばかり工夫して、人間の感情を掘り下げて描くことのない作品が多い気がするんです。愛する人が死んで悲しい、病気が辛い、犯罪は悪い、みたいな条件反射的な感情の作用ばかり狙った小説が増えている現状に、小説も魅力ってそんなところにはないんじゃないかという、もう、バンカラ魂に近いような憤りがあるんですよ。
玄侑 バンカラなんて言葉、久しぶりに聞いたなあ(笑)。
道尾 天の邪鬼かもしれないし、おこがましいかもしれないけれど、せめて自分は流行に流されないで、古いスタイル、絶対になくしちゃいけない小説の価値を守りたいという気持ちがあるんです。
玄侑 そうか、だから道尾さんの小説には、形はいろいろあれど、行き着くところにあらまほしき人間像というのが示唆されていて、温かく好ましいものを感じるんですね。それは道尾さんの言葉だと「救い」を描くということなのかもしれないけれど、私も小説を書く上で、そういう価値観ってゆるがせにできないものだと思っているんです。道尾さんが思うように、いまやそれはクラシックなものになってしまっている?
道尾 間違いなくクラシックですね。言葉を換えれば、書かれても売れない。
玄侑 それでもなおそういう小説を書こうと思う、いちばんの動機というか、コアにあるものって何ですか。
道尾 僕にとっては、「ある人物の感情を書いてあげたい」という衝動ですね。
玄侑 ある人物というのは、最初からはっきりしている?
道尾 はっきりしている場合もあるんです。たとえば『月と蟹』の場合だと、慎一という主人公――その時点ではまだ名前のない、歳も少年ということしか決まってないような存在ですけれど、彼が如何ともできない世界の不幸、不安と向き合い、彼ひとりでは抗いようのない閉塞状況に追い込まれたときに、それでもこの世界に踏みとどまろうとする、その瞬間を描きたかったんです。 |
|
| |
|
|
| |
物語からの夢通信 |
|
| |
|
|
| |
玄侑 そのコアの感情というのは、どういうふうに浮かんでくるんですか。
道尾 何でしょう、うーん……難しいなあ。僕、何を書こうかと考えているときに、よく夢を見てボロ泣きすることがあるんですよ。それは、小説で描くべき感情の芽のようなものを、もしかしたら夢で見ているのかもしれません。
玄侑 夢ですか、それは面白い。私ねえ、昔、夢の自動筆記をやっていたことがあるんですよ。アンドレ・ブルトンの本を読んで、へえ、そんなことできるのかなと思って、ためしに枕元にノートを置いて寝てみるんです。
道尾 へえ、自動筆記。
玄侑 ええ。夢を見たなと思ったとき、あらまし半覚醒の状態でその内容を書き取る。それを何度もやっていると、だんだん書き取りつつも夢から覚めないようになっていくんですよ。で、ちょっと書きとめて寝ると、また同じ夢の続きが見られるという、そういう練習をしたことがあって。
道尾 そんなことができるんですね。
玄侑 夢の世界って、私の今の職業にふさわしい言い方をすると、あの世につながっている。あの世というのは、いろんな言い換えが可能だと思うんですけども、目に見えない世界であり、この世の価値とはまったく違う価値を持った世界です。で、私もものを書くときは、あの世に触れながら書いていると思うし、できればそこに読者を連れて行きたいなあと、そういう気持ちがあるんです。伝統的な考え方でいうと、夢も神懸かりも一緒なんですよ。人間って、この世じゃない世界をどこかで求めていて、そこに連れて行ってくれるのが神懸かりであり、夢であり、ときに小説であるかもしれない。その媒介となる存在を、昔の中国人はたとえば龍とか白雲とか鳳だとか、あれこれ創造したわけですよね。
道尾 なるほど、そうですね。
玄侑 だから、夢で何かを感じるというのは、あの世と通信しているんだから、解釈しきれなくて当たり前。
道尾 証明のしようもないので、それこそ“夢のある”解釈ができますよね。理系の本を読んでしまうと、願望充足だとか記憶の断片だとか、夢を自分の意識の中にあるものに還元していこうとするんだけれど。
玄侑 自我に引き寄せて合理化しすぎると、つまらないでしょう。
道尾 そうなんです。僕が最初に聴いた池袋の講演会で、たしか玄侑さんは夢の話をしてらして、夢枕に女性が出てきたとき、平安時代はその女性が自分のことを思って夢に出てくるという解釈をした。ところが今は自分が相手のことを思っていると分析する。同じ現象でも解釈の仕方が百八十度変わってしまったと。
玄侑 平安時代の解釈のほうが絶対に面白いでしょう。それに、ある意味で、謙虚な見方だとも思います。
道尾 ああ、なるほど、私の意識がすべてを決めているわけではない、決められない、という発想ですもんね。
玄侑 ええ。道尾さんが夢で見るというのも、物語のほうから道尾さんに向かって通信してきているのかもしれない。
道尾 面白いですね。自分でも不思議だなあと思うんですけど、僕、自分の見る夢と、書いている小説とがすごくリンクしているんですよ。『ラットマン』を書いているときも、用いているトリックの大きな欠陥に夢の中で気がついて、朝起きてあわてて原稿を直したことがあるんです。 |
|
| |
|
|
| |
自分をおだてる |
|
| |
|
|
| |
道尾 先日、NHKのBSで玄侑さんの特番を観たんですが、壁につきあたったとき何度も挑戦して壁を突き破るんじゃなくて、壁があったらまず横へ行ってみるというお話をされてましたよね。二十代の終わりから三十代にかけて、まるっきり小説を書かない時期があったと。
玄侑 はい。もともと小説を書きたくて、この寺も継ぎたくなかったんですよ。でも、結局約束の時までにデビューできず、観念して修業に出て、三十代の十年はまったく書かずに、坊さんの仕事に専念してたんですね。そして四十代になって、急に小説が書けるようになって。
道尾さんは三十歳までにデビューしようと思っていたんでしょう? サラリーマン時代、営業の仕事をやりながら小説を読みふけってたっていうのを、エッセイで読みました。
道尾 そうですね。営業車の中でずーっとサボりながら、読んだり書いたりしていました。
玄侑 太宰治の『人間革命』を読んで、小説を書こうと思ったと。
道尾 それが十七歳の頃です。本を読まない子供だったので、『人間失格』が人生でほぼ初めて読んだ小説で、活字でしか描けないものがこの世にあるんだと目から鱗が落ちるような思いがして、小説を読むようになりました。実際に自分で書いたのは十九歳のときですね。書いたものは、戯曲だったんですけど。
玄侑 どうしてまた戯曲を?
道尾 若い時代特有の勘違いで、戯曲って舞台で演じられるものだし、決まりごととか制約がたくさんあるから、かえって書くのは簡単だと思ったんです。
玄侑 その後、道尾さんが小説を書き始めたきっかけは何ですか。
道尾 いろいろ小説を読んでいるうちに、あ、これ自分が書いたほうが絶対に面白いなと思ったんですよ。世の中の評価は別として、自分の趣味に百パーセント合うものが、自分で書けばそこに存在するわけですから、じゃあそれを読んでみたいと。
玄侑 戯曲の前に、『緑色のうさぎの話』という絵本も描いていますよね。エッセイ集に収録されているのを拝見いたしましたが、あれはどういうきっかけで?
道尾 十七歳の頃に書いたもので、たぶん何者かになりたかったんでしょう。自分が何の才能を持ってるかいという気持ちが強かったんです。ギターを持って金髪でライヴ活動なんかもやってたんですけど、音楽の才能なんてどれだけあるかわからないし、勉強もそんなにできないし。そういえば、人形を作っていた時期もありました。
玄侑 人形ですか?
道尾 石塑っていう、固まるとカチカチになる石粘土でボディを作って、そこに和紙で着物を着せ、小さな家を拵えて、精巧なジオラマを作るんです。それを一眼レフで写真に撮るんですけれど、要するに、何か自分が持っている才能をみつけたかったんです。何も持っていないのは寂しいんで、何かあるはずだと思って、いろんなことをやってみようと。
玄侑 絵本も、才能があるかもしれないと思ってやってみた?
道尾 たぶん。まあ、あれ一話つくってみて、僕の才能は絵本じゃないとわかった(笑)。でも、それはまさしく玄侑さんが壁にぶつかったのと同じだと思うんです。人形もそれほどではなかったし、絵本もうまく描けなかった。でも、ほどほどのレベルのまま二作、三作と続けていこうとは全然思わなかったんです。僕は昔からしょっちゅう勉強をサボッたり、仕事をサボッたりしてたんですけど、絶対に人生だけはサボらないという信条を、十代のころから持ってたんですよ。
玄侑 人生をサボらない?すごい言葉ですね。
道尾 社会人になってもそれは変わらないくて、人形や絵本がダメでも、小説を書く才能はあるかもしれないと。
玄侑 道尾さんのいうサボらないというのは、クリエイトすることなんだ。
道尾 そうです、何としても自分の才能を見つけ出すということ。
玄侑 なるほどねえ。
道尾 絶対に何かあるはずだって、幼い願望かもしれませんが、ずっと信じていたので。
これも先日の玄侑さんの番組で観て、なるほどと思ったんですけど、天龍寺で八日間、坐禅を組み続けるという修業をされたとおっしゃてましたね。
玄侑 「臘八大摂心」ですね。ほとんど寝ない坐禅を組むんだけど、普通なら三日くらいでダメになるんです。で、ダメになるだろうと思って臨むと、本当に三日でダメになるんですね。逆に、自分は絶対にできると思い込むと、面白いことにできちゃうんです。
道尾 心を変えれば、それに体はついてくるというお話でした。
玄侑 あれ、要は、自分で自分をおだてるということなんですよ。
道尾 あ、そうか。僕の場合も、おだてるという言葉に近いですね。信じるというとちょっとカッコよすぎるので、自分を一生懸命おだてて、試行錯誤を続けていたということですね。 |
|
| |
|
|
| |
「俺は書ける」と二十回 |
|
| |
|
|
| |
玄侑 その意味でいうと道尾さん、受賞直後に『情熱大陸』という番組に出られて、たいへん興味深いことをおっしゃっていましたね。毎朝、執筆前に自分を鼓舞するために、「俺は書ける」「俺は書ける」と二十回繰り返してるって。あれ、本当なんですか。
道尾 ええ、まあ……。『シャドウ』を書いているときに始めて、それ以来やめるのが怖くて続けているだけなんですけど、手段としては昔からあるトラディショナルなやり方ですよね。口に出して言ってみるというのは。
玄侑 ええ、ほとんど呪文ですね。
道尾 この間、すごく面白い話を聞いたんですけど、五円玉をテーブルに立てさせる実験があるんですって。三十秒の間に五円玉をテーブルに立ててくださいと言うと、多くの人が失敗するらしい。ところが、同じ人数の別グループに五円玉と糸を渡して、五円玉を立てて穴に糸を通してくださいと言うと、五円玉を立てるところまでは、ほとんどの人ができちゃうらしいんですよ。
玄侑 なるほど。五円玉を立てるくらいのことは当然できるだろうけども、さらに糸を通すのは難しいよ、という話し方をするわけですね。
道尾 そうです。それだけでまるっきり結果が変わっちゃう。人に言われてそうなるんだったら、自分自身に暗示をかけることもできますよね。そもそも小説を書くこと自体、自分が書いたほうが絶対に面白いという思い込みからスタートしているので。まあその勘違いが十七年間続いてるのは、我ながら大したもんだなと思いますけど(笑)。
玄侑 『情熱大陸』の最後で道尾さんが見せた表情、私、忘れられないな。
道尾 どんな顔でしたっけ。
玄侑 毎朝「俺は書ける」と唱えるっていうことを語るとき、なるほど、本当にそうかもしれないぞ、と思わせるような繊細で不安そうな顔をなさった。
道尾 えー、そうでしたか。
玄侑 でもね、番組のラストにあの表情があったから、道尾さん、ものすごく愛すべきキャラになったんですよ。
道尾 ハハハハ。
玄侑 番組の前半は、さほど苦労もなさそうに小説を書いて、直木賞をとるって宣言もしちゃう、ビックマウス作家という触れ込みだったでしょう。あのまま番組が終わったら、すいぶんイメージが悪かったと思う(笑)。最後の最後で、ああ、道尾さんにもあんな面があったんだって、ミステリーのようなどんでん返しがありましたから。
道尾 僕、作家デビューして七年目なんですけど、丸六年かけて築き上げてきたキャラクターがあれで一夜にして崩壊したような気がしましたよ(笑)。 |
|
| |
|
|
| |
事実は小説より奇なり |
|
| |
|
|
| |
道尾 僧侶を主人公にしている玄侑さんの小説の場合、たぶんお仕事が同時に小説のテーマにもなるわけじゃないですか。そのあたり、どういうふうにバランスをとってらっしゃるんですか。
玄侑 坊さんをやってるときって、たぶん作家のときとは人が変わるんだと思うんです。枕経(死者の枕元でお経をあげる儀式)の場に行って、創作意欲を刺激されるというのも、ちょっと困るじゃないですか。
道尾 なんだかありあたくない気がしますよね(笑)。そこでメモをとるわけにもいかないでしょうし。
玄侑 だから、私の場合、実際には、用事でどこかに出かけたついでにたまたま見たこと、聞いたことが小説の役に立つことが多いですよね。なりゆきとか、偶然があったから書けたっていう感謝は常にあります。それに、自分が意図して取材したことよりも、期せずして起こる偶然のほうがいいってこと、意外に多いでしょう。
道尾 それ、わかります。
玄侑 ある道尾さんの作品評を読んでいたら、物事が都合よく起こりすぎるんじゃないかという指摘があったんです。だけど、信じられないくらい都合よく変なことが起こるのも現実じゃないですか。文字どおり「事実は小説より奇なり」で、偶然に恵まれることが、小説を書く上でありがたい力になるんじゃないか、それも実力のうちじゃないか、と思うんです。
道尾 「事実は小説より奇なり」って、僕のいちばん好きな言葉でもあるんですよ。偶然の面白さをしっかり認識して初めて、現実より面白いフィクションが書けるんだと思っています。 |
|
| |
|
|
| |
小説のシンクロニシティ |
|
| |
|
|
| |
玄侑 私、「朝顔の音」という短篇で、死産した子を山に棄てた女性のことを書いたんですけど、実際に、近くの湖で子供の遺体が遺棄されて、このお寺に運ばれてきたことがあったんですよ。
道尾 湖のほとりに棄てられていたんですか?
玄侑 ビニール袋に入ったまま、湖畔に打ち上げられていたんです。ビニールの内側には水蒸気がびっしりついて、外から見ても何だかわからなくて、開いてみたら子供だっていうので大騒ぎになった。「朝顔の音」は、そういう経験からつくっていった小説なんですね。
道尾 玄侑さんはふだんから人の生き死にに接してらして、そういう経験をもとに小説を書くのって、やっぱり度胸というか、覚悟がいりますよね。
玄侑 だから、あんまり「もとに」して書かないほうがいいんじゃないかとも思いますよね。もちろん見たこと、聞いたことは次々に思い出せますが、いざ小説を書くときは、案外そこを避けてという気持ちが働くことが多いかもしれない。
道尾 じゃあ、その避けてという気持ちが、物語を生みだす原動力になっているんでしょうか。
玄侑 そういう面はあるでしょうね。私たちの仕事って、人が亡くなるたびに物語を作るんです。亡くなった人についてのお話を家族から聞いて、それこそ、何人兄弟の何番目で生まれて、どこに戦争に行ってというところから人生のあらましを聞いていく。その物語を文字にして、戒名を作るんです。
道尾 すると、物語を作るというのは毎日の僧侶の仕事でもあるんですね。
玄侑 ええ。これを毎日やってますとね、亡くなった人のために作った物語に、不足だあよな、と思うときがあるんです。この人の人生、この戒名じゃあ、まだ言い尽くせていないなと。その、申しわけなさみたいなものが、小説を書く源になっているのかもしれません。十年以上小説を書いていなかった私が、四十を過ぎて「水の舳先」を書けたのは、無意識のうちに供養が足りないという気持ちの蓄積があったのかとも思うんですよ。
道尾 さっき、『人間失格』の話をしたでしょう。高校生のとき、僕に太宰を薦めてくれた女の子が、じつは九年前に薬をのんで自殺してしまったんです。
玄侑 ああ……。
道尾 その子はショートカットで、僕がやっていたバンドのドラムだったんですね。で、『ラットマン』を書いたあと、その子のお母さんから「本当にありがとう」って連絡があって初めて気づいたんですけど、僕、『ラットマン』の中にショートカットの女の子のドラマ―を出しているんです。その子の父親がジャズドラマ―というところまでまるっきり現実と一緒で、それなのに僕、本が書店に並んで、お母さんから連絡をもらうまで、そのことにまったく気がつかなかった。もしかしたら無意識のうちに、彼女に対して申し訳ないような気持ちがどこかにあったのかななんて、後から思ったんですけれど……。
玄侑 申し訳ないという単純な感情じゃなくて、おそらく、もっと複雑なものでしょうね。
道尾 彼女は鬱病を患っていて、病院にも通っていたんだけれど、僕はそのころ勤め人だったので、連日夜中に電話がかかってきて「疲れちゃってさ」みたいなことを言われても、当時は死んじゃうなんてまさか思ってないものだから、正直、煩わしくて、ちゃんと対応してあげられなかったんですね。
玄侑 そういうシンクロニシティって、私にもときどきあって、本を出すと、自分のことを書いてくれてありがとうというお便りをよくいただくんです。
道尾 まるっきりの勘違いなんですか、それは。
玄侑 たまたま同じような状況にあってそう思い込んじゃう場合もあるだろうけれど、いずれにせよ、まったく知らない方から連絡をもらうんですよ。
道尾 お話を聞いて思うのは、いま流行っている小説って、誰が読んでもある程度は自分のことが書かれていた、ほどほどに気持ちよく感情移入できる。でも、誰一人深くシンクロできる人はいなくて、五人読んだらみんな二十点をつけて合計百点というような小説が多いんじゃないかと思います。でも、玄侑さんの小説は、たとえ四人が0点をつけても一人は百点をつける人がいる。その一人が、いてもたってもいられずに連絡してきているんじゃないでしょうか。
玄侑 四人が0点はひどいなあ(笑)。でも太宰治がどこかで書いたんですけど、殺したいほど憎いやつがいたとした場合に、その人が読めば必ず自殺してしまう小説を自分は書くことができる。逆に、何としても救いたい人がいたら、その人が読んで必ず元気になる小説を書くこともできる。小説ってそのくらい怖いものなんだなあというのは、今になってしみじみわかりますね。
道尾 そういう怖い小説が、もっと書かれてほしいし、残ってほしいんです。自分が読みたい小説を自分で書いているっていうことを言いましたけど、僕が好きな小説って、探してみると絶版になっていたり、本屋さんのキャパシティから漏れていたりすることが多いんですよね。
玄侑 それはそうですよね。
道尾 少なくとも僕は、バンカラ精神を忘れないで、四人から0点をつけられても、一人が百点をつけてくれる小説を書き続けたい。どこかの誰かの、百パーセントど真ん中に届くものを書き続けていきたいなあと思います。
玄侑 今まで、その誰かというのは自分自身だったんでしょう?
道尾 そうです。今後もそれは、究極的には自分だけなんだと思います。小説を書くのはけっこう大変なので(笑)、やっぱり自分のためじゃないと努力はできないですね。 |
|
| |
|
|
| |
誰にとっての「救い」か |
|
| |
|
|
| |
玄侑 道尾さん、そういう発言を繰り返しなさっているので、どこかで崩したいなという意地悪な気持ちが頭をもたげてくるんです(笑)。このままきれいに対談が終わっちゃうとつまらないので、『情熱大陸』に負けないよう、この対談でも道尾秀介の尻尾を掴んで、何かどんでん返しがほしい(笑)。
道尾 いやいやいやいや、怖いですよ(笑)。
玄侑 では、最後にひとつ伺いましょう。「救い」を書くということを、道尾さんは一貫しておっしゃっていますね。
道尾 はい。
玄侑 一方で、自分のために小説を書くともおっしゃっている。ということは、素直に考えれば、道尾さんは自分を救うために小説を書いていると解釈できそうなんですけど、いかがですか。
道尾 うーん、それはないと思うんですよ。ポーズではなくて、本当に。
玄侑 じゃあ、「救い」というのは、最終的には誰の救いなんですか。
道尾 僕は、物語は物語として捉えていて、そこに自分を重ね合わせたり、反映させたりはしていないんです。
玄侑 ということは、物語の登場人物の救いということ?
道尾 そうですね。作り上げた主人公たちが愛おしいから、彼らを救ってやりたいと思います。でも、書くことで僕が救われようという発想はないんです。
玄侑 なるほど。じゃあ、こう訊きましょう。道尾さんは少年を描くことが多いですよね。で、ほとんどの場合、その少年たちは親との葛藤を抱えている。このことは、道尾さん本人とまったく関係ないんでしょうか。
道尾 そうですねえ……まあ、僕自身の育った家庭があんまりまともじゃなかったために、自分の中に、家族の暖かさに対する憧れと、そんなものはどこにも存在しないという屈託と、ふたつ同時にあるということは確かだと思います。
玄侑 だとすると、そんなふうに言われたら心外かもしれないけど、道尾さんは小説を書くことで、幼いころの自分の何かを無意識に救っているのではいか。小説の中で、しんどい家族関係がわりと多く描かれるのは、道尾さんの中にある家族への負の感情がエネルギー源になっているような気もするんですよ。
道尾 それは……そうかもしれません。たぶん、家族への憧れと屈託とが両方あるので、ギッタンバッコン、引っ張りあう運動が起こって、物語を動かす原動力になっているのかもしれないですね。
先ほどの『ラットマン』の話みたいに、まったく無意識で書いていて、後に指摘されてハッと気づくこともあるので、もしかしたらいつか、ああ、あのとき対談で玄侑さんがおっしゃってたのはこういうことかもしれないな、と思うときがくるかもしれないです。ただ、なかなか自分では客観的に分析できないですね。僕としては、これからも自分のために、自分が面白いと思う小説を書き続けていくしかないと言えないです。
玄侑 それはそうでしょうね。今日は道尾さんと小説のお話ができて、楽しかったです。これからも必ず読みますから、面白い小説を書いてください。
道尾 ありがとうございます。僕も玄侑さんの小説、楽しみに待っています。 |
|
| |
 |
|
|
「オール読物」2011年3月号 |
|
|
|
|
|
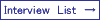 |
|
|
|
|