|
 |
 |
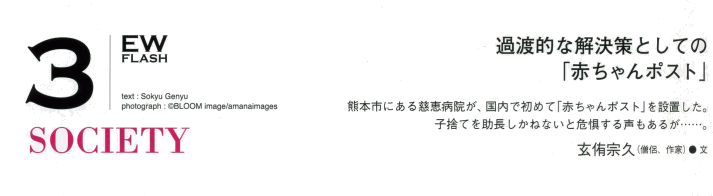 |
 |
|
|
|
|
昔は、産んでしまえばなんとかなるさ、という楽観が社会に支配的だった。「案ずるより産むがやすし」ということわざも、その経験的実感に支えられていた。
しかし今や、育てられそうもないから中絶する、という考え方のほうが常識的であるようだ。
むろんそれとて、最近始まったことではない。江戸時代から「間引き」は多かったし、その罪悪感から子安地蔵や水子地蔵などが日本各地に作られた。本来は大地の恵み、つまり「五穀豊穣」を担当していたお地蔵さまに、子供を見守る役割が加わったのはそのような時代からである。
中絶は、今や罪に問われない。しかしギリギリまで迷い、決断ができずに産んでしまい、その後に嬰児を捨てると、「保護責任者遺棄罪」に問われる。実際に増えつつあるそのような親と子を、救おうとして始まったのが「赤ちゃんポスト」という取り組みだろう。それにより、中絶件数が減ることも期待されているわけだ。
しかし実際どれほどの胎児が中絶されているのかが分からないと、この問題は考えにくいかもしれない。
私のお寺にも毎年産婦人科のお医者さんが、堕ろした子供の供養を頼んでくる。やはり気になるのだろう。1年でおよそ四百人の嬰児を取り上げるその産院で、堕ろされるのは270人ほど。むろん年によって多少の差はあるが、だいたい200人以上300人以下である。
あるとき、お医者さんに訊いてみた。「正式な夫婦の子供は、そのうちどのくらいなんですか?」皆さんならどんなふうに想像されるか知らないが、答えは「約半分」とのこと。つまり、主にバースコントロールのために、100人以上の胎児が毎年堕ろされているのである。 一つの産院で、毎年600〜700人以上生まれるはずの子供が、400人まで絞り込まれている。全国産院での中絶件数の合計など、けっして出てこない数字だろうが、それはおそらく想像を絶するものだろう。
その現場を知り、しかも一方では子供ができない夫婦のために人工授精などの技術が駆使される現場も知ってしまうと、「赤ちゃんポスト」の発想が出てくるのも自然なことではないだろうか。
じつはこうしたポストの機能は、第二次大戦後間もないころには日本各地の市役所や役場が請け負っていたことがある。親を失う子供たちが大勢現れ、その里親を紹介して斡旋する仕事を、やむを得ずかもしれないが、行政が請け負っていた時代があるのである。実際私の周囲にも、役場から里子に出されて育てられ、今も元気に暮らしている人が複数いる。
むろん私は、だからといって「赤ちゃんポスト」をどんどん推進してほしい、というわけではない。初めてポストに預けられたのは3歳の子供だったようだが、そうなると、ただの捨て子と何も変わらない。社会全体が大きく変わってきたなかでは、ポストの是非だけを単独に考えてもたぶんラチが明かないのだろう。
欧米では多くの国がポストを黙認する現状だが、2002年、オーストリアで匿名の出産を容認し、養子斡旋を可能にする制度を整えたところ、ポストの利用が激減したらしい。問題の鍵はその辺にあるのではないか。ポストは過渡的な在り方として行方を見守りたい。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
「日経EW」2007年7月号(日経ホーム出版社) |
|
|
|
|
|
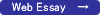 |
|
|
|
|