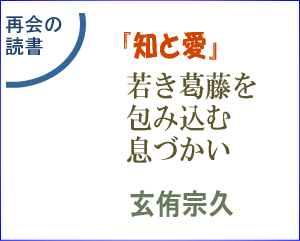 |
||
図書館分類学の棚のように、ただ宗教と文学を知ってはいたものの、自分のなかの衝動はもっと未分化で、渾沌としてはいなかったか。 たぶん本来は生きるための力が、出口のないままに鬱積し、自分自身を苦しめていたのだろう。今になれば、若いということは本当にやるせないことだと思う。 高校生のときに読んだヘルマン・ヘッセの『知と愛』は、そんな鬱屈した私が夢中になった本だった。 それより少しまえ、宮澤賢治に読み耽ったこともあったが、賢治に言葉の力を教わったとするなら、ヘッセにはもっと幅広い、いわば生きていくことそのものの息づかいを習ったように思う。 『デミアン』や『夢のあと』、『荒野の狼』、『シッダールタ』など、ヘッセの本はいろいろ読んだ。しかし後年、ヘッセへの恩義はいつも『知と愛』に集約される。 なにより、自分のなかの渾沌として出口のない欲求を、ヘッセは知と愛とに分化して見せてくれた。そのことに、私は感謝したい。 清らかな知と戒律の使徒であるナルチスと、美と愛を追い求めるゴルトムントは、おそらくは双つながら人の中に棲んでいるのだろう。ヘッセも、きっと自分のなかの葛藤を、二人に託して物語を進めるのだ。 私のなかのナルチスが、禅の修業への道を歩ませ、ゴルトムントが文学に関わらせる……。単純にそう考えることもできる。 しかし私にはその二人が分けられなかったからこそ、両方の道を歩んだのだろう。両者が知と愛の象徴である以上、たぶん人は、片方だけでは生きていけないし、じつは宗教も文学も、知と愛の両方がなければ成り立たないのだ。 宗教と文学の間の葛藤と見えた私の鬱屈は、『知と愛』を読みながらするすると解けていくようだった。両方を包み込むヘッセの息づかいに、私は大いなる安らぎを覚えたのである。 描かれる修道院とゴルトムントの旅には、おそらく全てがあった。ラテン語を初めとする堅実な学問、自然、戒律、そして恋や性。むろんそれらは多くの人間模様として慈しむように丹念に描かれていく。 正直なところ、それは今の私にとっては緩慢するほどのテンポである。 しかし、まだ学問も性も知らなかった当時の私には、それはどうしても必要な手続きであり、豊かな緩やかさだったのだと思う。 ヘッセに描かれると、多くのショッキングな出来事も事件性を失う。ヘッセは事件の連続としてではなく、むしろ思ったほどには展開しない人生上の時間として、さまざまなエピソードを描きたかったのだろう。若き日々の時間は、実際そのようなものではなかっただろうか。 最近どうも、そのような小説が少なくなったと思うのは、私だけだろうか。 見方によってはこの小説は、抽象と具体の物語と見ることも可能かもしれない。 むろんナルチスも具体的現実を生きてはいるのだが、それは揺るがず、秩序だち、しかも反復される。彼はそして思索と概念を愛している。ゴルトムントのように美を追い求め、多くの女たちの具体を愛する旅人にとって、それは抽象にも等しいのだ。 ゴルトムントは、いたる所で女たちに熱望され、幸福にされたが、同時に絶望も味わい、疲弊する。 それは恐らく、ヘッセにとっての生活が、具体への愛だけでは済まず、しかも概念だけでも成り立たないという暗喩ではないだろうか。 実際のところ、小説というのもこの両者がなければ成り立たない。いや、それこそが人間という生き物の厄介さではないだろうか。  しかしこの小説ほど概念的に堅固な小説も、最近は見かけない。ここに出てくるナチルスとゴルトムントの如き議論は、なんだか学生運動の盛んだった時代を彷彿させる。日本の学生運動とは、もしや抽象と具体を性急に合一させようとした運動ではなかっただろうか。 さて長い旅から修道院に戻り、ナルチスと再会したゴルトムントはどうなるのか。知と愛は、抽象と具体は、どのように折り合うのか。それはご自身で読んでお確かめいただきたい。 |
||
| 「本の時間」2007年3月号(毎日新聞社PR誌) | ||