|
|
|
|
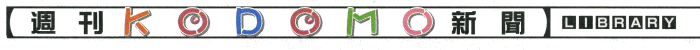 |
|
|
|
|
|
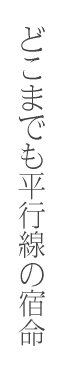 『私は人の顔をジロリと見る悪い癖があるのだそうだ。三十三の年にさる女の人にそう言われるまで自分では気づかなかったが、人の心をいっぺんに見抜くような薄気味わるさで、下品だという話だ。それ以来、変に意識するようになり、ああ、又やったか、そう思う。なるほど、我ながら、卑しい感じがする。魂の貧困というようなものだ。男にはメッタにやらぬ。自分では媚びるような気持ちのときに、逆に変にフテブテしくジロリとやるようなアンバイであるらしい。然し、どんな時にジロリとやるのだか、自分にも明確に分らず、その寸前に、ああ今、やるな、と思うと果してジロリとやるグアイで、意識すると、後味の悪いものだ。 『私は人の顔をジロリと見る悪い癖があるのだそうだ。三十三の年にさる女の人にそう言われるまで自分では気づかなかったが、人の心をいっぺんに見抜くような薄気味わるさで、下品だという話だ。それ以来、変に意識するようになり、ああ、又やったか、そう思う。なるほど、我ながら、卑しい感じがする。魂の貧困というようなものだ。男にはメッタにやらぬ。自分では媚びるような気持ちのときに、逆に変にフテブテしくジロリとやるようなアンバイであるらしい。然し、どんな時にジロリとやるのだか、自分にも明確に分らず、その寸前に、ああ今、やるな、と思うと果してジロリとやるグアイで、意識すると、後味の悪いものだ。
けれども三十三の年までは、自分のことには気がつかず、女の人が私に対して、そうするのだけが、ひどく切なく胸にこたえて仕方がなかった。すべての女の人が私にそうするわけではない。あるきまった女の人だけがそうで、(中略)そういうタイプの女は、私と性格的に反撥し、一目で敵意をもったり、狎れがたい壁をきずいたりするふうで、先ずどこまでも平行線、恋など思いもよらぬ他人同士で終るべき宿命のもののようだ。』
| (角川文庫『肝臓先生』48〜49ぺージより) |
 |
迷ったあげく、引用は冒頭部になってしまったが、ここにはすでに主人公の因業なあり方が透けて見える。人から言われた言葉に、卑下や冷静な観察がからまり、それは深い思想とも言えそうな居直りへと昇華されている。
「ジロリの女」というタイトルに惹かれ、私は20代に読んだのだが、まるで求道のように不得意なタイプに突き進んでいく主人公の行く末は、私にとっても怖いもの見たさ、しかし見届けずにはいられず一気に読んでしまった。
一読、聖と俗の境界はなくなり、女性や人間というものが、余計わからなくなった覚えがある。むろん男だってわからない。しかしわからないままに歩む決意にこそ、やがて赦しは訪れる。
まるで宗教小説の解説のようだが、実際「俗」のなかにしか「聖」はないのだろうと思う。この小説は、やはり切ない求道の物語だ。
|
|
|
|
 ジロリの女 ジロリの女
主人公の40代の男、ゴロー三船は、知的で気の強い女性を「ジロリの女」と呼ぶ。そういうタイプの女性は、心も見抜くように三船の顔を冷たくジロリと見るからだ。誰にでも軽口やお世辞を言う調子のいい男、三船は、苦手な「ジロリの女」たちに好かれようと、ひたすら努力を続ける。物語の初めに、三船は自分の過去を紹介する。 |
|
|
|
|
|
さかぐち・あんご
1906〜1955。新潟県生まれ。作家。作品は『堕落論』『白痴』など。 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
読売新聞 2007年10月20日 夕刊 |
|
|
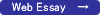 |
|
|
|
|