| |
|
|
| |
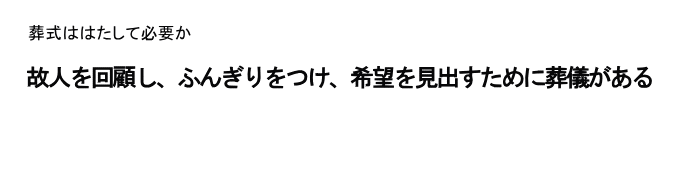 |
|
| |
歴史的かつ日常的な関係で成り立つ「布施」 |
|
| |
このところ、葬儀が要るの要らないのという議論が盛んである。正直なところ、私はこれまでそんな視点で葬儀を考えたことは一度もなく、考えるまもなく一〇〇歳のお婆ちゃんの自宅でお通夜である。
しかし不要論も必要論も読んでみると、どうも不要論の云う「葬儀」は、私のしている葬儀とは違うものなのだと気づいた。
これまで私は、のべ一〇〇〇人以上の方を見送ってきたが、全く知らない人の葬儀はおそらく数件しかしたことがない。弟が埼玉で亡くなったとか、妹が九州で亡くなったとか、あるいは生まれたばかりの子供など、むろん本人を知らなかったことはあるが、結局は兄貴が檀家さんだったり、よく見知った親族の依頼で葬儀をしたのである。
当然、檀家さんとか歴史的かつ日常的なつきあいがある。毎日の食卓に檀家さんから頂いた食べ物が載らないことはないし、盆暮れの心付けもおかげさまでいろいろ頂戴する。時には一緒に旅行などもするから、檀家さんについては趣味や特技まで知っている。これからお通夜に伺うお婆ちゃんの場合も、逆縁で亡くなった息子さんは見送っているし、若くして亡くなった旦那さんのことは先住職から聞いている。一〇〇歳生きた本人についても、よく歩き、よく耕した笑顔のお婆ちゃんだったから、戒名に入れる「天鍬」の文字が、お知らせを聞くうちに自然に浮かんできたのである。
そのような関係のなかで亡くなった人を見送るのが私にとってのお通夜や葬儀であり、戒名であり、当然その家の経済状況もよく知っているから、謝礼は「お布施」でおいくらでも、ということになる。
当家にすれば、毎年お寺の決算報告書も見ているから、お布施が何かの代価ではなく、それによってお寺が運営されていることも知っていてくださる。あくまで自主的に額面は決めていただくわけだが、少し悩みながらもそれほど奇妙な額にはならないものである。古いと云われるかもしれないが、私はこの代価でない「布施」というシステムがとても大事だと思っている。単純な基準や多寡では計れない価値が、本当はもっとあるべきなのだと思う。
|
|
| |
「葬儀のようなもの」では「布施」が「代価」に |
|
| |
しかし今、主に都市部で行なわれている葬儀(のようなもの)は、全く事情が違うのではないか。
普段お寺とのつきあいもない「宗教的浮動層」とも呼ぶべき人々は、身内の突然の死にまずは葬祭業者に連絡する。場合によっては、病院で待機していた契約会社の霊柩車で、すでにその会社の会館などに運び込まれているかもしれない。
そこでお寺はどうしますかと訊かれ、かろうじて憶いだした故郷の菩提寺の宗派を告げると、「お任せください。こちらで手配できます」などと言われる。「はい、よろしく」としか答えようがないだろう。
当然そこでは支払うべき「代価」が求められており、しかも葬祭業者が何割かをピンハネする構造になっている。そうして雇われて出向く僧侶がいったいどういう暮らしをしているのかは知らないが、どうやら各宗取りそろえてあるらしいのである。
故人にそれまで会ったことがないだけでなく、おそらく今後遺族とも二度と会わないような葬儀を、どうやってするのだろう。誰にでも同じような、当たり障りのない同じ香語を読みあげるのだろうか。
俗名ならともかく、そういう人の戒名はどうやって付けるのだろう。また受け渡しされる金額は、お布施ではなく代価なわけだが、それなら時給で考えても高すぎはしないか。
お寺という施設に媒に、歴史的かつ日常的な関係で初めて成り立つ「布施」を、このような通りすがりの関係で主張するからおかしなことになる。どうせ代価なのだからと、「定額制」の主張が出てくるのも当然である。
こうして考えてみると、今の世の中には我々のしているような葬儀だけでなく、それに似たようなものがあり、葬儀不要論は間違って「葬儀のようなもの」を「葬儀」と呼んでしまったのではなかったか。そんな戒名、そんな葬式なら要らない、という話なら私にもわかる。
ただ葬儀不要論を読んでみると、そこには残された人々の視点が欠けていることも指摘しておきたい。
我々とて死後のことはわからない。葬儀は愛する人をまとめて回顧し、なんとか「ふんぎり」をつけ、安心とまでは云わないまでも、なんとか仄かな希望や生きる力を見だすためにこそある。少しでもそのことに思いを致すならば、ちゃんとした葬式が不要だという理屈は出てこないはずである。
四十九日には様子をうかがい、お盆にも棚経に出かけ、我々と遺族とのつきあいはその後も続いていく。一度かぎりのビジネスチャンスとしての「葬儀のようなもの」と一緒に括られては困るのである。
|
|
| |
先祖や子孫を気にしない「寺のようなもの」 |
|
| |
戦後、日本人の生活状況はたしかに大きく変わった。これは高齢者なら今でも覚えている急激な変化ではなかっただろうか。
市場経済の流入。都市への人口集中、生活の快適化、それに伴って人と人との距離は離れ、地縁・血縁の関係もどんどん薄れていく。最近では「おひとりさま」でも暮らせるシステムがどんどん充実し、要するにご近所や親類どころか家族の助けも不要な暮らしが商売として準備されている。孤独死や無縁死も増えるはずである。
「隣は何をする人ぞ」も今や昔、隣人の頭越しにインターネットが広がり、そこではあらゆるものが買えるため、引きこもっても充分生きてゆける。テレビも電話も個人用、バーチャル世界でセックスから墓参りまですることができる。さらに核家族化ばかりか少子化も進む。そんななかで、葬儀だけが昔どおりに行なわれるはずはないだろう。
市場経済に飲み込まれた「葬儀のようなもの」においては、懐かしい「葬式坊主」が本当に登場してしまった。葬式屋と呼んでもいいが、彼らのなかには、過疎化で生活ができず、都会に流れてきた本物の僧侶もいるらしいから困ってしまう。
私も一度呼ばれて講演したことがあるが、彼らの一部は新興宗教のように先祖や子孫を気にしない個人の関係を結び、一つビルの中で葬儀から埋葬、さらには説法まで行なって人気を集めたりする。
先祖は重すぎ、子孫は当てにできないこの時代が、おのずから産みだした「寺のようなもの」なのだろう。
|
|
| |
本物の葬儀屋さんと菩提寺を探す方法 |
|
| |
葬儀のようなもの、寺のようなものが、すべていけないと申し上げたいわけではない。今はおそらく玉石入り乱れて割拠する葬儀の戦国時代のようなもので、いずれ自然な淘汰も起こるだろう。実際、新規参入の大手業者の心ないやり方には、地縁を重視する昔ながらの葬儀屋も困っているのである。しかし市場原理での淘汰が、必ずしも善なるものを残すとは限らないので、一言だけ注意を申し上げておきたい。
菩提寺を探す場合、法事などの「価格」を表示しているところは信用しないほうがいい。市場原理に迎合し、六波羅密の第一である「布施」を説くことをやめた寺はすでに仏教寺院ではない。
また会員半額など、やたらな値引きを売り物にする葬祭業者も信用しないほうがいい。そんなことで喜ぶより会員獲得の真の目的と、元値を考えてみるべきだ。
消費者のためといって廉さばかりアピールする業者が、結局は儲けしか考えていないのは、今や他業種にも共通するだろう。個別性にまったく応じる気もなく、会館でのパックを押しつけるばかりの葬儀の素人が、あちこちで「葬儀のようなもの」を売りはじめた昨今なのである。 |
|
| |
|
|
| |
※1 逆襲
子が親より先に逝くことの意だが、じつはこれは転用。もともとの意味は、仏法を言葉や行為で謗るなどしたことが、後になって仏に帰依するきっかけになることをいった。他に、生前の仇敵を供養すること、親類縁者でもない人間が供養することの意味にも使われる。そこから、因果や道理に違背する意味に使われるようになった。
※2 香語
禅宗の法要で唱えられる言葉(法語)のうち、とくに焼香の際唱えられるもの。拈香法語、引導法語、引導香語ともいう。一般に漢詩の形式をとることが多い。
内容は仏教説話や経典を交えつつ、故人の業績を讃えるもので、法要の季節や故人の年齢、性別、人柄などによってさまざまなバリエーションがある。最近は、季節や年齢などを選択するだけで、ふさわしい香語が自動的に作成できるパソコンソフトもある。
※3 残された人々の視点
葬送では、遺言やエンディングノートなどで伝える故人の遺志がもっとも重要視されるが、葬儀を行う意味は、遺族や関係者が愛する人を失って感じる喪失感や悲しみなどのようにして乗り越えるという側面にこそある。
かつてノンフィクション作家の柳田那男氏は、脳死移植の是非をめぐる議論に、愛する家族を亡くした人の「二人称の死」の視点が欠けていることを指摘した。葬儀もまた、「一人称の死」や「三人称の死」からだけでは語れない。
※4 棚経
盂蘭盆会の時期(七月一三日~一五日、または八月一三日~一五日)、寺の住職が遺族の家に赴き、お盆用にしつらえた精霊棚の前であげるお経のこと。精霊棚がなく、仏壇の前であげるお経も、この時期には「棚経」という。檀家に出向いて行うようになったのは江戸時代からとされる。住職が一年で一番忙しい時期だ。
※5 六波羅密
菩薩の六つの実践徳目。簡単にいうと、持てるものを他に与える「布施」、奉仕や笑顔を惜しまない「持戒」、目標に向かって一筋に進む「精進」、迷いを絶ち、よく見て熟慮を重ねる「禅定」、悟りに到達する「智慧」。仏さまの教えを守り、自他を救う法門である。人智を超えた境地に到達する「解脱」が目的。
|
|
| |
 |
|
| |
「日本の論点2011」(文藝春秋) |
|
|
|
|
|
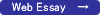 |
|
|
|
|