| |
このところ、私たちは日本という国が火山列島であったことをにわかに憶いだしつつある。三・一一以後、余震がやまず、それが活火山を刺激することを怖れているのだろう。
三陸沖の海底に、何キロにもわたる亀裂が入った写真を新聞でご覧になった方もいらっしゃるかもしれない。あれで落ち着いたとは誰にも思えないし、次は東南海、南海沖地震は想定され、そのときは富士山までも連動するだろうと、地震学者は言う。
実際、富士山の三大噴火の一つとされる宝永の大噴火(一七〇七年)でも、大地震があり、大津波が来て、四九日後に噴火している。このときにできたのが新幹線から見える。南東山腹の宝永火口である。
年代が推定できる最も古い富士山の噴火の記録は、『続日本記』にある天応元(七八一)年の降灰の描写だが、それ以前の万葉人にとっても、すでにこの山は「神の山」「宝の山」であると同時に、「燃える山」だったようだ。『万葉集』巻一一には、次のような歌がある。
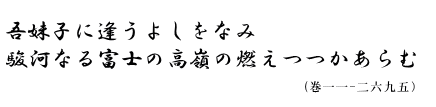
富士山の喩えを用いた以外には、とりたてて変わった主旨はないが、とにかく愛しいあの子に逢う手がかりがないので、この人の心は活火山の富士山のように爆発寸前に燃えさかっているのだ。「燃えつつ」の原文は「燒管」だから、溶岩が土を焼くような状態なのかもしれない。
ちなみに二番あとの二六九七では、逢って噂が立つと困るので、やはり富士の高嶺のように心の中で燃え続けていようと歌われている。なんと富士山は、ここでも忍びつつ燃える恋の象徴なのである。
二〇〇九年一〇月、GPSによる観測で、静岡県富士宮市と山梨県富士吉田市の間の距離が二センチ伸びたことが確認され、地殻変動によるマグマの蓄積が明らかにされた。いよいよ危険なことは確かなのだ。
しかしだからといって仕事も恋もせずに漫然と待機しているわけにはいかない。万葉人の子孫としては、恋はしながらエネルギーを使いきらず、いざという時は想定して凛然と暮らすしかあるまい。時に噴火し、時に忍びつつ、高く美しくなった、あの聖山のように。
そう、富士山の希少さは、何よりも噴火しつつ高く成長したことだ。もしかすると、それが日本の恋のかたちか……。
|
|