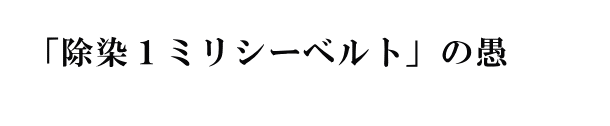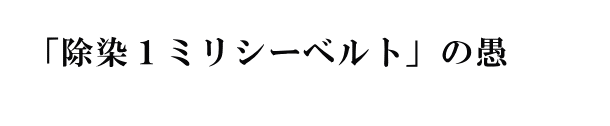|
先日、NHKの「視点・論点」という番組で「除染に思う」と題して話をした。訊かれもしないのに一人で語るという非常に恥ずかしいスタイルなのだが、それを聞いてくださった花田編集長が、ありがたいことにあの話をもっと弘めるべしとの思いを抱かれ、連絡を下さった。少し視点を変え、新たな情報も加えつつ書いてみたい。

震災から二年が経ち、現在の福島県を眺めてみると、まず気になることは、この三月にどれほどの幼稚園児や小中学生が戻ってきたのか、ということである。
震災から一年あまり経った二〇一二年四月、つまり一年前の郡山の幼稚園児は約二割減り、小学生は約一割減少していた。いずれも、低線量被曝による被害を恐れた主に県外への避難のせいである。
同じ線量を、危険だと見なす人々と、住み続ける以上問題ないと思うしかない人々との乖離は、どんどん広がっていった。そして、国はその事態を招いた責任をどう考えているのか、抜本的な解決策を考えようとはせず、怖がる人には怖がるままにその生活も支援し、しかも怖がられたその場所に国際会議を誘致したり多くのイヴェントを開くなど、いったい危険なのか安全なのかはっきりさせないままに事態を複雑にしてしまったのである。
事の発端は、二〇一一年四月に行われた計画的避難区域の設定と、学校の校庭で遊ぶための基準設定の齟齬だったような気がする。年間二十ミリシーベルトを超えたら計画的避難区域だと決める一方で、文科省は当初、年間二十ミリシーベルトを超えなければ校庭でも遊んでいいと宣言した。遊ぶ時間を考慮し、毎時三.八マイクロシーベルト以下なら遊んでかまわない、と言ったのである。
いくらなんでも、同じ値を少しでも超えたら避難せよというのに、少しでも下回れば子供に遊んでいいという話は無茶である。それに抗議する人々が、県内の父兄をはじめ大勢で文科省の前に坐り込み、基準は「年間一ミリシーベルト以下」にすべきだと訴えた。やがて、内閣参与に採用された元ICRP(国際放射線防護委員会 )の委員、小佐古敏荘氏が四月二十九日、涙の記者会見をするに及び、文科省は抗議を認める形で「一ミリ以下」という基準値に変更したのである。
しかし、この「年間一ミリシーベルト」という数値は、元々間違った計算式によって導かれたものだった。長年の疫学調査の結果から、百ミリシーベルトを超えると初めて発癌率が0.五%上がるとされる。そのため一生の間に百ミリを超えなければいいと考え、一生を百年として百ミリを百年で割ったのである。
この考え方のおかしさは、何よりその後どんどん分かってきた人間の細胞の修復力を考慮していないことにある。低線量の被曝は、あらかたその日のうちに修復されてしまうから、実は年間の累積を問題にする意味はほとんどなかったのである。
また、小佐古氏が政府に提出した文書には、「年間五ミリ程度が妥当な規制値」との内容が書かれていたらしく、なにゆえ彼が突然一ミリに固執し、記者会見で泣いたのか、未だに謎とされる。しかし、少なくともICRPの委員たちからは、彼の行為が「これまでの学問的蓄積を無にした」と批判されているのである。
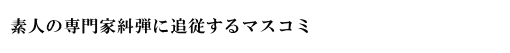
その頃までに、小佐古氏の涙ながらの発言を歓迎した人々は、次々に専門家たちを糾弾していった。
長崎大学から福島県立医大の副学長として招聘された山下俊一氏も、県の放射線健康リスク管理アドバイザーとして各地で講演を繰り返したが、途中から安全を説くほどに批判を浴び、やがては怒号に包まれるような場面も経験する。
管見だが、おそらく山下氏には当時の福島県民の怯えが明確には理解できていなかったのだと思う。私自身もそうだが、当時はまだ原発自体が爆発するような危惧を払拭しきれなかった。現状の数値だけでなく、それが急変しかねないという怯えが続いていたのである。いわゆる専門家であるほど、この程度の数値で怖がる必要はない、と説いた。いまになればそれは結果として正しかったのだと判るのだが、しかしその言い方があまりにもTPOを心得ていなかったのだろう。いわゆる専門家たちのほぼ全員が「御用学者リスト」に入れられてしまった。素人が専門家たちをジャッジし、マスコミもそれに従った。学問にとって、こんな不幸なことがあるだろうか。
その間に過敏な意見を振りまいた人々のなかには、どう見ても放射線防護学、生物学、影響学などの専門家はいなかった。そして二〇一一年七月、一見、専門家と思えるアイソトープ研究所所長、児玉龍彦氏が衆議院厚生労働委員会でこれまた涙ながらの参考人発言を行なったことで、悲観派はその意を強くする。さらに『内部被曝の真実』という脅しのような彼の著書が、迷っていた多くの人々に県外避難を決意させるのである。
二〇一二年初めには、県外避難者が六万一千人まで膨らんだ。その年のうちに四千人程度は戻ったようだが、この春にはどれほど戻ってきてくれたのだろう。
私はこの事態の責任の一端が、マスコミにもあると思っている。素人と一緒になって専門家たちを埒外に追いやり、その復権に手を貸そうともしない。
国連の科学委員会が昨年十二月、福島原発事故後の検証結果を発表したが、簡単に言えば「認識できるような健康被害はなかった」という内容だった。ところが、これを大きく扱ったのは私の知る限りほんの一部のメディアに過ぎない。一体、これはどういうことなのだろう。
また、福島県内の十八歳未満の甲状腺検査の結果についても、これまでそんな検査は医師たちも未経験であったため、子供の成長過程で出現し、いずれ消えてしまうしこりのことなど全く知らなかった。他県との比較検証の結果、福島県の比率がむしろ低いことも判ったのだが、最初のショッキングな報道ばかりが蔓延し、それを否定する情報はあまり大きく報道されないのである。
いみじくも、私の知る編集者が言った。
「玄侑さん、安全は売れないんですよ。売れるのは危険なんです」
なるほど、そうなのだろう。フクシマは、いまやマスコミの大事な商品なのだ。
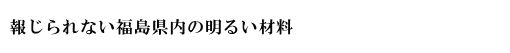
私自身、放射線のことなど、今回の事故以前には何も知らなかった。しかし、物書きの務めとしても、その後は必死に勉強した。いや、新しい事実も次々に判ってきているから、現在進行形と言える。
実際、福島原発事故以後に初めて判ってきたことも多い。たとえば内部被曝の半減期が、セシウム137の場合、三~四ヵ月とされていたが、これも年齢によって随分違うことが判明した。もともと言われていたのは成人男女の数値で、六歳児では一ヵ月で半減し、一歳児だと十日で半減する。チュルノブイリやスリーマイル島で小麦から類推していた稲のセシウム吸収率は、予測と全く違って低かったのもこのせいである。風雨の多い日本ではあるが、二年で半分近くまで線量が下がるなどと、誰が予測しただろうか。
県内に住み、安心材料を捜す私には、明るい材料が次々に見つかるのだが、マスコミはこれらを決して大きく扱うことはなかった。こんな問題にも、資本主義の論理が蔓延しているのだと思うと、本当にやりきれない。
しかし、落胆ばかりはしてはいられないから、私はいろいろ調べ始めた。まず、低線量の被曝影響についての学術論文を手に入る限り読んでみた。すると、少なくとも二十ミリシーベルト以下の線量については、浴びるとSOD酵素が活性化するなど、とにかくこんなに体にいい、という話しかないのである。
次に私は、文科省が全国のモニタリングポストの値を発表しないから、なんとか調べてみたいと思い立った。
二〇〇二年、長瀬ランダウア社が全国十四万九千ヵ所で測定し続けた値では、年間一ミリシーベルトを超す県が十一県ある。その数値を眺め、そして一九八〇年頃の全国の線量も調べてみると、私には驚くべき推測が浮かび上がったのである。
ただこの推測は、口にするにはまだ不確実な気がした。
そこで女房のアイディアで、三春町の「実生プロジェクト」の協力を仰ぎ、全国のお寺にOSL線量計を送り、各地の現在の環境放射線量を継続的に測っていただこうと思い立った。女房が毎日、全国のお寺に電話をかけまくり、宗派に関係なく、百以上のお寺が快く協力してくださった。むろん、その程度の数では、長瀬ラウンダウア社の調査と違い、その県の平均と考えるわけにはいかない。しかし、そういう地域もある、と知るには充分ありがたかった。
ちなみに、三春町の「実生プロジュエクト」は、子供たちの健康不安払拭のため、福島県内で最も早くから線量測定を開始し、いまもそれを継続している唯一の組織である。ご寄付を中心に運営しているのだが、全国の寺院線量調査にも予算をとってくださったのである。
その結果、判ってきたことは、やはり私の不吉な推測を裏付けるものだった。一九八〇年には岐阜県が全国一高かった放射線量だが、二〇〇二年の調査では富山県、石川県などに抜かれてくる。そして年間一ミリシーベルトを超えた十一県を地図上に並べてみると、どうしても線量変化の原因が西のほうにあるような気がして仕方なかったのである。
一九六三年、部分的核実験禁止条約が締結されたが、中国は加わらなかった。そして翌六四年からおよそ八〇年まで、地上と空中での核実験がウイグル自治区で繰り返される(八二年から九六年は地下実験に移行)。その間に地表に放出された放射能物質の総量は、調査に赴いた高田純氏の試算によれば、チェルノブイリ原発事故の約五百万倍だという。「核の砂」入りの黄砂が毎年、西日本から北陸にかけて大量に降っていたことは間違いない。そして、その推測を裏付けるように今回の寺院調査でも、福島の影響は考えられないような地域(熊本県、大分県、三重県など)で、年間一ミリシーベルトを超えてきたのである。埼玉県や千葉県などは福島第一原発の影響だろうが、新潟県まで超えてきたのはどちらの影響か微妙なところだ。
ただ私は、だから日本中が危険だと申し上げたいわけではない。文科省が全国のモニタリングポストの測定値を発表しないのは不満だが、それも尖閣諸島で揉めている現状を考えれば無理もない。隠蔽は不愉快ではあるが、それよりもいまはこうした現状なのに、福島県内の除染がそれでも年間一ミリシーベルト以下を目指すことに、驚きを通り越して呆れているのである。
もし今後も一ミリシーベルトを目指すというなら、私は声を大にして申し上げなくてはならない。それなら全国各地に除染の対象地区は無数にありますよ、と。
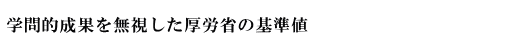
やっぱり目指すのは一ミリだ、という雰囲気は、二〇一二年四月の厚労省による基準値改訂によって明らかに強まった。当時、厚労相だった小宮山洋子氏によれば、「(暫定基準の)年間五ミリシーベルトでも安全は確保されていたが、子どもをもつお母さんたちが心配していたので、安心してもらうために年間一ミリシーベルトにしなげればならなかった」とのこと。ここにおいて専門家の研究成果は全く尊重されることなく、それどころか政治判断という名目で踏みにじられた。
その結果、食品中の放射性セシウムの暫定基準値も、「野菜類・穀類・肉・卵・魚等は一キロ当たり五百ベクレル、飲料水・牛乳・乳製品は二百ベクレル」から、新たに「一般食品百ベクレル、飲料水十ベクレル、牛乳・乳児用食品五十ベクレル」に変更になった。
特に飲料水の制限値は、アメリカが一千二百ベクレル、EUが一千ベクレルという基準値であることに比べると目を瞠る。それなりの学問的成果から導かれた数値を、いったいなにゆえ、そこまで無視できたのだろう。小宮山氏は、いまでも「この基準値のままでいい」と主張し、「世界に誇れる基準」だとするが、いったい何を誇るというのだろう。こうなると、単に潔癖症が一日何度も掃除することを誇るようなものだ。
ちなみに、日本の美味しい水百選に選ばれた水が、最高で九十九ベクレル、最低0.二四ベクレルあり、多くが今回の基準値を超えていることを厚労大臣はご存知だったのだろうか。
放射線審議会長だった京大名誉教授・丹羽太貫氏は、この件の最終審議で厚労省の提出した新基準値にあらためて疑問を呈した。しかし厚労省は、放射線審議会の意見にも農水省の見解にも耳を貸さず、最終的には食品衛生管理について自分たちが責任者だからと、生産者の都合や放射線についての学問的集積さえ無視したのである。
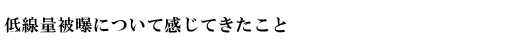
低線量被曝という、学問的に「よくわからない」領域の扱いに関していつも感じてきたのは、いわゆる医学界の「インフォームド・コンセント」の悪弊である。「インフォームド・コンセント」自体は、受診者が医療者から充分な医学的説明を受け、そのうえで自己判断することだからまともな理屈である。しかし現実には、医療者と患者の間に医学的知識の差がありすぎ、また医療者が忙しいこともあって「最悪のことまで話しておく」という意味に変形している。たとえば、盲腸の手術前にも死亡例について聞かされる、そうすれば死んでも訴えられない、という意味に変形して使われているのである。
だから低線量被曝についても、よくわからないのだから最悪に考えておいたほうがいい、という態度が、どうやら「知的」な人々の基本姿勢になってしまったのだ。
むろん、遠くに住んでいるのならそれで済む。しかし、その考え方で福島県に住み続けるのは難しいのである。
国連科学委員会(UNSCEAR)は、今回の除染の在り方にも苦言を呈している。自然放射線量を年間二.五ミリシーベルトから三.五ミリシーベルトに上げても発癌率は上がらず、逆に一ミリシーベルトに下げても発癌率は下がらないことがわかっているなかで、なにゆえ一ミリを目指すのか。そのために「兆」というお金を注ぎ込んでどうするのだろう。
専門家である彼らは、たとえば砂糖も塩も大量に摂取したら死ぬから、砂糖も塩も一切禁じるという愚かな政策を批判するような馬鹿馬鹿しい無力感さえ感じているのではないだろうか。しかもお金は無尽蔵ではなく、他に必要な場所が無数にあるのである。
最後に、やはり原子放射線の影響に関する国連科学委員会の二〇〇〇年の報告書から、面白いデータを紹介しておこう。人口分布とその土地の自然放射線量が判る表なのだが、それを見ると、たとえば年間一.五ミリ~三ミリシーベルトの線量域に住む人々が、イタリアでは全人口の七一%ハンガリーでは五三%、デンマークでは六九%、ベルギーではなんと七六%、香港では驚くなかれ八五%に及ぶのである。日本の場合は、基礎データがどこから行っているのか知らないが、やはり半数以上、五二%の人口が一.五~三ミリシーベルトエリアに住んでいる。一.五ミリシーベルト以下の地域に住んでいる日本人は、全体の四八%である。
一ミリシーベルトを目指す除染とは一体何なのか、もう一度考えてほしいのである。

福島県内では、あちこちにブルーや黒のフレコンバックが今日も増えつつある。中間貯蔵施設も決まらないまま、除染で出た土や草、丹精込めた苔や庭木の枝までが、田舎では道路脇、都市部では庭の一角に袋詰めで置かれているのである。
こんなせつない景色はこれまで見たことがない。それは学問の無力さ、政治の無知と横暴、メディアの無責任など、実にさまざまな思いを喚起させる。総じて言えば、せつなくて仕方ないのである。
もう二年の時間が経ったのだから、あらためて専門家たちにきっちりと、今度は泣かずに考えを述べてほしい。メディアもいまさら「危険」など売り物にせず、真の復興のための智慧を絞ってほしいのである。
停電や汚染水漏れなど、このところ福島第一原発の未収束状況が露わになりつつある。毎日四百トンも出る汚染水の処理のほうが、除染などより遥かに喫緊の課題であることは間違いない。
|