 其の参拾二 其の参拾二 |
||
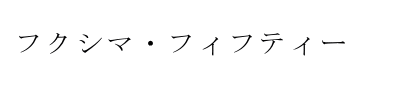 |
||
| 福島第一原発が津波によって全電源を喪失したとき、施設には約六千人の従業員がいた。そのうち約二千人が六基の原子炉の立ち入り制限区域無いで作業を行なっていたという。 五号機と六号機は定期点検のため冷温状態だった。しかし一号機から四号機までの四基は稼働中(四号機は分解点検中)であったため、そのまま送電停止が続けば原子炉内部の核燃料が手冷却できなくなり、熱で溶け堕ちて大量の放射性物質を放出する可能性があった。 津波の翌日の三月十二日午後以降、一号機から次々に水素爆発が起こってくる。このとき施設内部の人々の恐怖感はいかばかりだったかと、今になって思うのである。一部の協力会社は社員を撤退させ、また津波で家を流されてしまった従業員も多かったため、家族を捜しに出て行く社員たちもいた。結果としては吉田昌郎所長以下、数百人の人々が現場に残って戦うことになったのである。 「吉田調書」によれば、吉田氏は「東日本壊滅」さえイメージしたらしい。またイギリスのザ・ガーディアン紙の取材に答えた吉澤厚文氏のように、「特攻隊員のように、自分のすべてを事故処理に捧げる覚悟」だったともいう。吉澤氏の言葉を再録しておきたい。 「留まることを強制された人間は一人もいませんでしたが、その場にいた全員が、最後まで取り組み続けなければならないと解っていたのです。原子力発電所を守れる人間は、私たちだけだと解っていました。考慮の余地などなかったのです」 彼らの捨て身の奮闘によって、東日本、いや世界が救われたと言っても過言 ではないだろう。風呂にも入れず、ビスケットや乾燥食品しか食べられず、しかも床が堅くて眠れない。血圧はたちまち上がり、顔色の悪くなる人も多かったという。 アメリカのABCニュースやニューヨーク・タイムズは、いち早く「フクシマ・フィフティー」として彼らを顕彰し、多くの海外メディアも採り上げた。五十人どころかその数は数百人もいたのだが、どういうわけか、日本ではほとんど顕彰されることもなく、スペインの皇太子が授与した「共存共栄賞部門(平和賞)」も、推薦された「福島の英雄たち」からいつしか東電社員が外され、自衛隊、警察庁、消防庁だけが代表で受け取ったのである。 事故の責任のこともあるのだし、東電社員を英雄にしてはいけないという思惑が、どこかから圧力として働いたのだろうか。それも解らないではないが、こうした捨て身の働きぶりを顕彰しなかったことで、その後の被災地に「雄々しさ」が失われていったように思われる。 国や東電という組織の問題はあるにしても、「それはそれとして」今も続く現場の果敢で雄々しい作業員たちに、あらためて感謝したい。 |
||
| 東京新聞 2014年11月1日/中日新聞 2014年11月15日【生活面】 | ||
| 次回へ | ||
| |
||