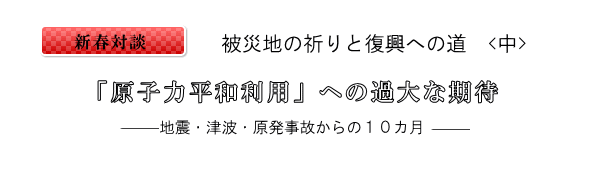 |
||
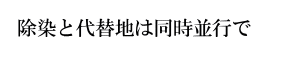 理想のエネルギーで人類の未来はバラ色なんだということを、アメリカやソビエトが相争いながら同じ宣伝をしている。それに対して、まさに自分のやっている学問が大きな力を発揮できる時だ、と物理学者が前のめりになっている。 1954年にビキニの核実験があり、非常に大きな警告があった。にもかかわらず前のめりが続いていた。どうしてそうなったのかを考えるヒントがそこにはあると思います。 そういうことへの危機意識を強く持っていたのは、アインシュタインであり、ハイゼンベルクであり、あるいは朝永さんであったということを唐木順三という人が言っています。 飯舘村の村長さんが二重の住民票というやり方を国に要求したんですね。飯舘村に属しながら今お世話になっている行政にも属して、福祉などのサービスも受けられる形にしてもらったので、双葉町の人も今いるところにお世話になりながら所属は双葉町という状態が続いている。 第1回の復興構想会議の時に「これはユダヤ人状態ですよ。彼らの町、村というのをどうしていくのか」と聞きました。チェルノブイリの場合は無数とも言える町や村が無くなった。「もとこういう町がありました」という看板だけがある。そうしてしまうつもりなのかを聞いたんです。 第13回の集まりが久しぶりにあって、同じことを復興大臣に聞いたけれども、答えられない。新たに国有地を切り開いて、双葉町の人はここに集まってはどうかというような場所を用意しなかったならば、町は無くなります。 今住んでいるところで新しい仕事を始めている人もいるわけですから、溶け込んでしまう。全員が町や村を離れて今いるところに溶け込んでしまったら、事実上、元の町や村は無くなります。そうするつもりなのかどうなのかを聞いたわけです。重大な問題だとい思います。 チェルノブイリの場合は50万規模の都市を新しくつくって、そこに幾つかの市町村から強制移住してもらった。しかし、その準備もなさそうです。このままだと日本全県に散った5万8千人が溶け込んだままになる。元の町が無くなるかどうかは、手を打たなきゃいけないことだと思うんですけどね。 これは広い場所があるということもあるし、強制的な措置に従わざるを得ない住民の状況もあったと思います。除染などをやろうとしても、それだけのマンパワーや技術がなかったということもあるんですね。 日本でも「早く疎開するべきだった」という方もしるし、「危険がないんだから残っているべきだ」という人もいる。その中で、取りあえず除染をしてみようということで、かなりのエネルギーが費やされています。 これは、ある程度理にかなっている。というのは、日本で除染をやってみるとどういう効果があるかは、やってみないと分からない。日本の技術力でできることがあるかもしれない。その状況がある程度見えるまで先の見通しがつかない。 好意的に解釈しているんですが、政府が優柔不断であるとも言えるけども、様子を見なければ分からないという面も少しはあるのではないか。 飲んだ時に「戻れるはずあるかよ」と言われると、自分の中で必死に「戻るんだ」という気持ちに仕立てているのに、それを言われたら聞き逃せない。それで大げんかになるらしい。 除染を進めることと、代替地をつくることは同時並行でやらないとどうしようもないと思います。除染が済むまでお世話になっている土地にずっと居続けたら、そこに根が生えてしまいます。 無理やり引き離されるような形で故郷から離れたわけですから、そのフォローとして両方必要なんだと思います。 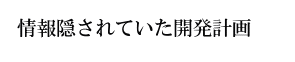 例えば食品の暫定規制値。「暫定」なんだから「いつか」までのはずですね。それはおそらく1年ぐらいの意味だということは初めから分かっている。しかし、それについて、いつまでも言わない。ようやく秋になって来年の4月ごろには基準を厳しくするんだと言いました。早く言っていればだいぶ違う。 学校の除染の20ミリシーベルトというのだって、ずっとそのままならたまらないとみんな思う。それをすぐ1ミリシーベルトに下げたりしましたが、長期的なビジョンを持ってしっかりとした方策を示すことができていない。 最近になって26頭の牛を20キロ圏から捕獲し、牛の体内にセシウムがどんなふうに蓄積するのかを東北大学の福本教授がチームで調べ始めた。こんなことが分かってきたのは世界で初めてです。 血中のセシウム濃度の何倍ぐらいがタンに行き、レバーに行き、と調べていくと、一番多いのは筋肉なんですね。そういうこともようやく分かってきた。 例えば降ってきた放射性セシウムがコンクリートやゴムとかプラステチックには付着するけれども、アスファルトには付着しないということだって分からなかった。暗中模索なんだと思います。 イギリスのセラフィ-ルドでは、いまだに家畜の線量が多いと食肉にはできず、元に戻して、安全なものを食べさせて出荷し直させるようなことをやっている。このイギリスの災害は1957年に起こっている。 それが情報の隠蔽とつながっている。その被害を日本は受けてきたわけですから、発展途上国にそのことを伝えるべきであって、「日本で原発でもうけることができないから、海外で売ってもうけよう」というのはほとんど詐欺に等しいと私は思いますね。 長期的には世界中に放射性廃棄物をばらまくことになる。福島県が何十年の単位で考えていますが、おそらく何万年とか、もっと長い単位の事柄なので、そこまで考えると、もう成り立たないことを正直に認めるしかないんじゃないかと思いますね。 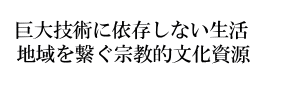 ――現実をみれば、原子力の利用が危険であることは明らかです。しかし。そのことを言えるのは宗教者のような立場の人しかいないのではないか。そういう意味でも宗教が果たす役割は、現実的に大きな意味を持っていると思います。 そのことは被災地を眺めると強く感じることで、ローカリズムというものを復活しないといけないのではないかという感じがすごくしています。 電力や食べ物も含めて、ローカルな範囲の中で「自治」という方向は必ず必要になっていくだろうという気がします。巨大なシステムによって失われてきたものは自治ですよね。 原発でこれだけの被害が出てきたことは、日本の国の大きな方針に何か見誤りがあったと同時に、私たち自身の生き方も反省しなくてはならないことがある。 アインシュタインも最初はナチスドイツに対抗するために原爆の製造をアメリカに要請した。しかし、ナチスが負けた後に日本に使われたことに非常なショックを覚えて、そこから平和運動に大変力を入れるようになります。その過程でガンジーに対する傾向を強めていったと言われています。 まさにガンジーのスワラージ、つまり自治ですね。巨大技術によらない生活というものを見直さなくてはならない。アインシュタインにはそういう先見の明があった。戦争の中とはいえ、前のめりの科学技術によって世界を動かすことに自分が動いた。一度動かすと止まらない。そのことにおそらく相当な衝撃を受けた。アインシュタインやハイゼンベルクのような人たちは、そういう考えを持っていた。 それに近い感じ方を日本の宗教者も持っていると思います。自分たちがこれまで歩んできた歩み方を振り返って、原発に対して問い掛け直すというやり方が宗教者としてはふさわしいのではないかと私も思っています。 岩手では「災害復興カレンダー」ができました。岩手の芸能の写真を集めて、芸能の復興に役立てようという。これはまさに地域社会の自然と密着した世界観、生き方と合わせて復興を考えようということです。 ですから、仏教の観点から言っても、神道の観点から言っても、新しい見方に転じていく文化資源が、われわれの受け継いだものの中にはたっぷりある。 |
||
| 中外日報 2012年1月3日 | ||
| 上 中 下 | ||
| |
||