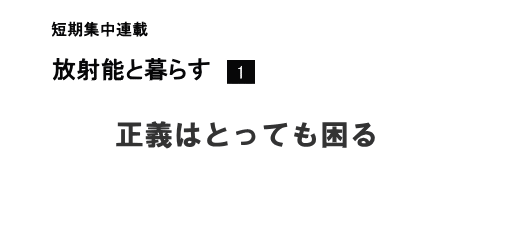 |
||
| 正義感にかられた女性からの「電話」は、福島の放射能を巡る問題を象徴するものだった――。 | ||
| いま、放射能のことは、福島県内には限らない世界的な問題である。私自身も、中国やフランスの国営放送、ドイツの週刊誌「シュピーゲル」、フランスの「ル・モンド」紙などの取材を受けた。あ、そういえば日本人記者ではあったが、ロイター通信の取材も受けたのだった。 小説を書いての取材ならいかにも誇らしいが、今回の場合、取材の理由は私がフクシマに住んでいることに尽きる。フクシマの人間は、どのように現状を認識し、どう感じているのか、彼らはそれが知りたいのだ。たまたまそこに適当な作家がいたということだろう。適当な、というのは、復興構想会議のメンバーでもあり、坊さんでもある。さまざまな視点からの意見が聞けると思われたのかもしれない。 ここでは、彼らに答えた内容をかいつまむつもりでご紹介したい。はて、なにゆえ外国人への説明を日本人にするのか、というと、認識がほぼ似たようなものだからである。具体を欠くと、人の思いはすぐに概念化する。外国からの取材陣にも、東京その他から来る人々にも、それは同じように感じたことだった。さすがに最近は、国内の取材の場合もう少し勉強しているが、事故当初はあまりにもフクシマ全体が一括りだったものだ。 尤も、マスコミはしばらく「福島第一原発」の所在する市町村名さえ言わなかった。誰もが、原発はフクシマ沿岸地域、という程度の認識だった。だからこそ「いわき市」や「南相馬市」には宅配便も通わず、最もとばっちりが激しかった。川内村宛ての荷物を運転手が怖がり、私の住む三春町の役場に置いていく、などという事態も発生していたのだから、県内在住の運転手さえ危険区域が限定できなかったということだろう。外国のメディアがフクシマを一括りにしたのも無理はなかったのかもしれない。 本題に入るまえに、三月中に起きた非常に困った出来事について、書いておきたい。これはたしか『震災日記』にも書いたと思うが、ある女性団体のメンバーを名乗る女性が、電話をよこした。着信番号を見ると、どうやら九州である。私より年上と思えるその女性は、「どうして町の人たちを連れて、逃げないんですか?」と詰問調で言う。私はこの町の状況を話し、ライフラインも繋がってるし、線量もそれほど高くないのだと説明した。しかし彼女は、どうもNHKの「ラジオ深夜便」での私の話を聴いたらしく、「国は信用できない」「逃げるべきだ」と繰り返した。 ご心配いただいてありがたいと御礼を述べ、私は最初の電話を置いたのだが、翌日彼女の話していたホームページを覗くと私との会話が不正確にUPされている。やがて電話はほぼ毎日かかるようになり、どんどんその時間も遅くなっていった。夜中の三時に電話が来たとき、さすがに私は怒鳴りつけた。その後ピタリと電話が来なくなったのだが、しばらくは嫌な感じが続いたものだ。 さて、こんな話を枕に置いたのは、これから書こうとするフクシマの放射能を巡る問題にとって、この話がとても象徴的だからである。 一つは彼女があまりに具体的な現実を知らないこと。二つ目は彼女があくまで正義感にかられてそうした行為に及んでいることである。 正義はとっても困る、とだけ、ここでは申し上げておこう。 全てが信用できない 現在、福島県では、放射能を巡って非常に複雑な状況が発生している。 ご承知のように、国は四月二十二日、警戒区域の外側に、計画的避難区域を設定した。その基準は年間被曝量が20 mSv を超える恐れのある地域だ。当該地域は一ヶ月以内に避難するようにということだった。ところが文科省はすでに四月十九日、子供たちの通う学校の校庭などについて、やはり年間20 mSvを下回れば遊んでいいと、県に通知していた。 これはいったい何の冗談なのか、怒った市民団体は五月二十三日、文科省前での抗議デモに及んだ。しかもその時点で原子力委員会は、年間20 mSv という数値は認めていないと逃げてしまっていた。孤立無援の文科省はそれでも基準値を変えず、やがて郡山市を先頭に校庭の土を削ぐ動きが起こり、処分の当てもない土は校庭の片隅に次々仮置きされていった。そうして文科省は、とうとう八月二十六日になって基準値を変え、ようやく平時の国際基準である「毎時1μSv未満、年間1 mSv 未満」に修正した。それを目指したすべての活動経費も、国が負担することになったのである。 結果オーライのように見える一連のこの経過だが、ここでまずこの国は、本気で子供を守るつもりなどないのだと見なされ、信用を失った。その後、状況はどんどん複雑になっていくのだが、すべて の源にこの出来事があったように思える。 年間20 mSv という数字は、ICRP(国際放射線防護委員会)やIAEA(国際原子力機関)が、緊急時における被曝限度量として設定した「20~100 mSv 」の最低線を用いたのだから文句あるまい、というわけだが、あくまでこれは緊急時の、しかも大人対象の数値と考えるべきだろう。細胞分裂の盛んな子供の場合、少なくとも大人の三倍以上の影響を想定すべきだとされる。そして文科省はこの数値のなかに、内部被曝量を算入していなかったのである。 ほぼ同じ時期に、原発の作業員の被曝限度量を年間50 mSvから250 mSvに引き上げたことも人々の疑いを深めた。そうしないと、作業そのものが成立しないから引き上げたとしか思えず、それなら学校の線量規定も、学校存続のための方便ではないか。そう思われたのだ。 こうした不祥事とも言うべき不手際な文科省の動きにより、県内の学校から転校する子供たちはどんどん増えていった。当初の避難指示や計画的避難などで、すでに二十三校が休校し、三十一校が移転を余儀なくされていたわけだが、運営されている学校からも子供たちは次々に離れていった。七月十五日時点で県内を離れた小学生は五千七百人あまり、中学生は千九百人あまりいたが、ほどなく一万人を超え、大人を含めた県外避難者は八月十一日時点で五万人を超えている。 さらに夏休み中は、私も関わった「ふくしまキッズ」プロジェクトが子供たちを北海道に「疎開」させたのをはじめ、富山、沖縄など、あちこちで支援者を得て、長期の疎開が実現した。 なんともありがたい救済策ではあったが、戻ってきても県内環境がさほど改善されていたわけではない。学校の校庭などは夏休み中に概ね毎時1 μSv以下にできたものの、通学路や自宅の周囲の除染は簡単なことではない。二本松市で乳幼児を抱えた家が市の助けも借り、家の周囲の土を五センチずつ削り、休耕田にしている自分の土地に運んだのだが、一軒分だけでその汚染土壌の量は三十トンにも及んだ。膨大な手間と経費がかかるうえ、最終処分場はもちろん中間処理場も決まらず、さらに市町村に委ねられた仮置き場さえ決められない現状である。 処分場については、政府内での意見の食い違いも垣間見える。八月、首相退陣直前、まるで最後のご奉公といった趣きで菅総理が福島県を訪ね、「放射性の瓦礫や土壌の中間貯蔵施設は県内でお願いしたい」と佐藤雄平知事に告げていった。しかし九月四日になり、細野環境・原発事故担当相は「最終処分場は県外に設けたい」と述べ、「福島県民の痛みは日本全体で分かち合うことが国としての配慮だ」とまで言ったのである。まるで沖縄の米軍基地問題を想わせる話だが、いったい細野氏は最終処分地としてどこを想定していたのか? その点について知り合いの閣僚に訊いたところ、どうも青森県の六カ所村らしい。 そんなことが了承されるはずがない。いま福島県民にとって最も懸念されるのは、中間貯蔵施設が最終処分場になることである。政治家の言葉がかつてなかったほど信用されなくなっているのだ。 やがて総理は野田佳彦氏に代わり、閣僚の多くが入れ替わったが、とりたてて進んだことがあるわけではない。しかし「福島の再生なくして日本の再生はございません」という就任会見の言葉は、やはり嬉しかった。総理の言葉で慰められる体験を、我々は久しぶりにしたのである。 同じ会見での言葉で、新総理は「原発事故の一日も早い収束」を誓ったわけだが、とにかくそのために、私は復興構想会議でも当該プラントの製造に関わっていない第三者機関を復旧作業に加えてくれるよう切望してきた。いつまでも企業論理(利潤追求が最優先)であらゆる発表がなされ、企業として不都合なことを隠す状態が改変されないからである。 なんと東電は九月二日、つまり野田内閣発足当日に、衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会に提出した「事故時運転操作手順書」全十二ページのほとんどを黒く塗りつぶしていた。また同委員会理事会に追加提出された「シビアアクシデント・マニュアル」A4判3枚のほとんども塗り潰されていたのである。この期に及んで、なにゆえこんなことが許されるのか。また原子力安全・保安院は、なにゆえこんな文書を受理したのか、まったく理解できない。 九月二十二日まで、国連本部で開かれていた「原子力安全首脳会合」で、総理は原発の安全性を「世界最高水準に高める」などと演説したが、そこでは同時に国連から県民の健康調査チームが派遣されることが決まった。また二十四日には、原発の事故調査・検証委員会に、海外の専門家を入れることも明らかになり、政府は「透明性の確保を国際社会にアピール」などと述べているが、どう考えてもこれは日本人だけに任せてはおけないという判断に思える。 実際、九月二十四日の東京電力の発表では、一号機の格納容器につながる配管に水素が充満しており、着火源さえあればいつ爆発してもおかしくない。また二号機、三号機の原子炉の上には濛々と蒸気が上がっており、これは専門家からの連絡で私個人は先月から知っていたことだが、発表が今ごろというのもどういう神経なのか。 要するに、もう全てが信用できないし、そんな東電を放置している国の在り方にも不信感がつのる。放射能の汚染については、こうした発生源の管理収束への不安も加わっている。 子供を苦しめる「予防医学派」 さて、ここからが本題なのだが、今フクシマの人々の心には何が起こっているのか、些か私見を申し述べたい。 まず総体として云えるのは、フクシマ全体を覆う「懶し(物憂し)」という気分だろう。良寛和尚は「生涯、身を立つるに懶く」と言って出家の頃を振り返ったが、フクシマ県民の場合は出家で解決するはずもなく、さらに深刻である。意志と関係なく突然に生活を断絶され、家や家族を失って仮設住宅に住む人々は勿論だが、それ以外の人々も先行きが見えず、信じられる情報が何かも分からない。おそらくこの「情報価値の暴落」こそ、菅政権が犯した最大の罪だろう。 先行き不安であるゆえの「ものうさ」を言うなら、原発被害に対する東電の賠償態度なども大いに関係するのだが、ここでは主に放射能がもたらす問題に絞りたい。 放射能の危険性については、これまで原発推進派が過少に見積もり。反原発の人々が過大に見積もる傾向があったわけだが、そうした定式は今のフクシマでは通じない。今、県民の殆どは脱原発の立場だが、同時にこれまでの暮らしがそのまま続けられることを切望している。つまり放射能については、できるだけその被害が微少であってほしいのである。 ご承知のように、年間の被曝量にして20mSvから100 mSvまでは、明確な健康被害を示す医学的見解がない。つまりデータがないのだ。それゆえ、この「分からない中間値」について、大きく分けて二つの立場からの主張がある。一つは「予防医学的」とも云える見方で、100 mSv以上は比例的に発がん率が増えるわけだから、それ以下も同じように見るべきで、放射線は少なければ少ないほどいいのだとする立場。もう一つは、一九八〇年にアメリカ、ミズーリ大学のラッキー教授が提唱した「放射線ホルミシス」説に基づく考え方で、塩分やホルモン同様、放射線も大量に受ければ死に至るが、適量なら白血球中のリンパ球も増えて免疫力も増すのだから、ある範囲内は体にいいのだ、とする立場である。 この両者は、お互い、医学的には証明できないために、ほとんどある種の信仰の様相を呈している。別な言葉でいえば、思い込みである。冷静に考えれば、神がいて救ってくださるに違いない、というのも思い込みなら、神などいないに決まっている、という無神論も反対のベクトルながら同じ思い込みである。妙な喩えかもしれないが、予防医学派とホルミシス派は、そのように議論も成り立たない関係として無言で対峙しているのである。 両者には、その考え方を支えてくれる感覚的な実感は勿論ない。放射能に色や匂いがあれば、長年生きてきた生命体として何らかの違和感や親和感をもつだろうが、それもない。だから判断の基準はあくまでも線量計の示すたまさかの数字である。 しかも予防医学派は、現実にはありえない線量ゼロを理想とするから、どこまでも不安はなくならない。ホルミシス派とて、理想の線量が措定されているわけではないから、議論はしたがらない。 そのような状態で、両者はフクシマの子供たちを挟んで対峙するのである。 主に県外からやってくる予防医学派が、むろん優勢である。「万が一」のことを考えれば、県外避難するに越したことはない。彼らのその理屈には、ホルミシス派ならずとも、放射線の観点から反論することは難しいだろう。正義は間違いなく予防医学派にある。ただフクシマに現実に暮らす人々は、ストレスについてはもっと総合的に考えなくてはいけないと、控えめに呟くだけだ。 実際、同じクラスの○○ちゃんも△△ちゃんも残っているのに、どうして私だけ出ていくの?という子供の問いに、きちんと答えられる親がいるだろうか。子供はたいていその疑問を抱えたまま出ていくのである。避難先の新しい学校で、差別を受けないとも限らない。そうなると、放射線から逃れた子供のストレスのほうが甚大ということにもなるのである。 注意しなくていけないのは、予防医学派の考え方そのものが、そうした差別に繋がっているということだ。差別する人々には、むろん放射能についての基本的無知が背景にあるものの、「万が一」のことを考えれば、内部被曝の可能性もあるフクシマの人々には接しないほうがいい、結婚相手としても考えるべきではない、となるのは当然の帰結なのである。 あくまでも大雑把な括りとしてだが、予防医学派がフクシマの子供たちを救おうとし、図らずも別な予防医学派がその子供たちを苦しめるのである。 予防医学派は殆んどボランティアで子供の移住斡旋から親の仕事の斡旋までしている。本当にありがたい善意だし、助けられたと感謝する人々も大勢いるだろう。彼らも自信をもってそうした活動を続けているかに見える。しかし、現実的な安全ライン、あるいは避難すべき線量限度をきちんと決められなければ、それは生活の細部を無視したイデオロギーになってしまう。 予防と差別の融合 イデオロギーを単に「物事に対する包括的な観念」と捉えれば、時にそれを必要とする状況もあることだろう。しかしそれは常に何らかの排他性をもち、自らの精力を拡大しようとする理想主義的運動体を形成しやすい。 今回の予防医学派も、人によってはあまり大括りに「東北の野菜や牛肉は食べるな」とまで発言している。ここにおいて予防と差別が、見事なまでに融合していることは誰に目にも明らかだろう。 現地の住民にとっては、そうなるともはや脅しでしかなく、細部を見なくなった人間の戯言としか聞こえない。現場では常に、「二本松の米には少し出たようだけど、本宮はどうなのか」、とか、「キノコは諦めたし、栗にも出たようだけど、胡桃はどうだろう」というような、具体的な話しか意味を持たないのである。 「地産地消」も一つのイデオロギーだろうし、我々だってそんなものに命を捧げるつもりはない。 今、フクシマに必要なのは、狭量な信仰やイデオロギーに陥らず、たとえ包括的な見方ができなくとも詳細に具体を見ながら対処することだ。 その際、どうしても必要になるのが暫定的ではない判断基準なのだが、それを発すべき主体がどこなのかさえも分からなくなっている。原子力安全・保安院なのか、文科省なのか、それとも官房長官なのか? いずれにしても一度失った情報の価値はそう簡単には戻りそうもなく、校庭以外の新たな基準値は出されそうもない。もともとIAEAにもそうした基準値はなかったというのだから事は簡単ではない。しかしそうして無力に逡巡するうちにも、正義の味方がフクシマの子供を放射線ストレスから別なストレスの中に連れ去ろうとしている。私にはいま、「夢のようなゼロ」を目指すこの正しき人々が最も怖い。 除染が一向に進まない状況ではあるが、合意できる一定の基準が決まればそうした動きはマットウな救済になるはずである。その基準づくりに際しては、一九六一年と六二年だけで合計一二八回も行なわれた世界の核爆発実験の影響なども、是非とも斟酌していただきたい。 今回の原発事故以前に、我々がどんな放射能生活をしていたのか、まずはそれを知って冷静になりたいものだ。 |
||
 |
||
| 「新潮45」2011年11月号 | ||
| 第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 | ||
| |
||