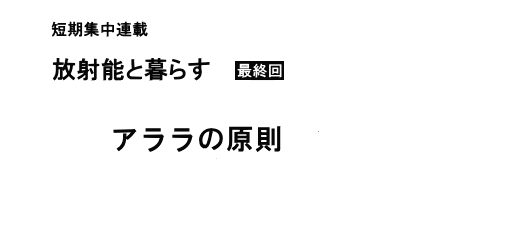 |
||
| 「年間1mSv」では福島県の再生はあり得ない。県民は専門家の現実的な説明を求めている。 | ||
| 正直なところ、福島県の現状はけっして「希望に燃えて」という状況ではない。毎日、新聞やテレビはさまざまな活動を紹介し、希望を持とう持とうと励ましてくれるが、どうも根本のところで気分が晴れない。少なくとも私はそうである。 二月十五日の「福島民報」の一面には「県復興計画停滞の恐れ」と載った。どうやら原因は、国が復興の青写真を描けないせいらしい。二月十日、ご承知のように復興庁が発足し、その業務が開始されたわけだが、担当職員によればあまりにも「検討すべき項目が多く、帰還に向けた支援策を市町村に説明できる状況にない」。「作業のスピードアップを目指したいが……」と口ごもるしかないのである。 確かに膨大な業務だろうと思う。新たな三区分(「避難指示解除準備」「居住制限」」「帰還困難」)の見直しとそのための除染工程づくり、上下水道や電力などのインフラ復旧、雇用対策、賠償方針の策定なども当然必要である。また住民が帰還できるためには、医療設備や機能を再構築しなくてはならず、なにより不足している医師や看護師を捜さなくてはならない。救急搬送を担う消防機関との調整も必要になるだろう。不動産買い上げを初めとする土地・家屋の補償システムも作らなくてはならないが、文科省に属する原子力損害賠償紛争審査会が明確な賠償方針を示さないため、これも先に進めないのだ。 また学校を再開するには除染が不可欠だが、これも優先順位づけに苦慮しており、たとえ順番が決まっても汚染廃棄物の仮置き場が決まり、さらには中間貯蔵施設が決まらなくては、便秘の人の食欲のようなもので、単純には喜べない。 前回の原稿で「ぐずつき」と表現したことが、ここに来て福島の現場であからさまになったように思える。 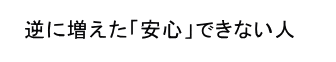 そんな暗中模索の一月三十一日、川内村の遠藤雄幸村長は、いち早く「帰村宣言」をした。二月十五日には野田総理に直接要望書も手渡した。原発事故のため役場機能の移転を余儀なくされた九町村で最も早く、この四月から学校や役場を再開するというのだ。とにかくそれは明るいニュースだったし、応援したい。そのための支援策を、復興庁には速やかに出してほしいと思う。 しかし私の感じる根本的な憂鬱は、どうやら遠藤村長の言葉に接しても晴れない。それどころか、より明確な形で、気鬱の原因が浮かび上がったような気がする。村長が指示したのは「戻れる人は戻る、心配な人はもう少し様子を見てから戻る」という柔らかな方針なのだが、ここには国の安全基準によっても「安心」できず、分断されるコミュニティの苦渋がはっきり垣間見える。 先日、三春町の仮設住宅に暮らす葛尾村の方と話す機会があった。私が「いま最も言いたいこと、訊きたいことは何ですか」と訊くと、その夫婦はこう話した。 「線量計もあるし、自宅付近やこの場所が毎時何マイクロシ-ベルトなのかは分かる。しかしそれが安全なのか危険なのかは、さっぱり分からない。いろんな学者が別なことを言うし、もう新聞もテレビも何も信用できない」 たしかにそうなのである。川内村でも、危険だと思って「少し様子を見てから戻る」人もいれば、「もう戻らない」という人もいる。葛尾村でアンケートをとったところ、三分の一は「戻らない」と答えたそうだが、そのほとんどが若い人々や子連れの夫婦なのである。はたして若者や子供のいないコミュニティが成り立つのかどうか、それが重大な問題である。 考えてみれば、こうした現状は、前回示した各省庁ごとのバランバラな基準が招いたとも言える。内閣府の開いた検討委員会が政府の暫定規制値を支持したのに対し、厚労省は新たに厳しい基準を設け、その多くは四月から施行される。さらに文科省は給食について別の基準値を設け、1kg当たり40Bq(ベクレル)と独立独歩で制限するのである。 どこまでも「安心」できない人々のために、「安全」基準のハードルを勝手に上げていった結果、逆に「安心」できない人々が増えてしまった。そういうことではないだろうか。いつのまにか決まった野菜100Bqはアメリカの基準の12分の1、水10Bqはなんと120分の1である。 今回は今さらの観もあるが、「安全」と「安心」について、あるいは「安心」のための合意形成について、あらためて考えてみたい。  今、世間には、「福島は危険だ」という見方と、「たいしたことはない」という見方が併存している。 心理的な背景としては、とても理解できる。つまり福島県を離れ、現在も余所の県に住む人々は六万人以上おり、その人々は今もそうして県外に居る根拠を、無意識的であれ求めている。彼らにとっての福島県は、危険でなければならないのである。 一方、さまざまな事情で県内に残っている人々は、「たいしたことはない」と思いたい。だから当然そのような考え方が支持される。 そして幸か不幸か、世間にはその両方を供給してくれる「学者さん」がいるのである。 以前、私は「予防医学派」と「ホルミシス派」という分類でその両者を示した。ここでは、もう少し詳しく両者の主張を検証してみたい。 本当は、両者が同じテーブルに就き、話し合いによって「合意形成」をしてくれれば一番いいのだが、どうやらそういうことにはなりそうもない。この国は、政治も含め、極めて合意形成の不得手な国になりつつあるようだ。 アメリカの核物理学者ワインバーグは、トランス・サイエンスという言葉で「科学によって問うことはできても、科学によって答えることはできない問題」があることを示した。しかも彼は「それでいながら意思決定をして、社会を動かさなくてはならないような問題が常にある」と言い、「原子力もうそうだ」と認めている。 データのない年間100mSv以下の被曝については、まさにそういった問題だと言えるだろう。しかし現状では、国の「意思決定」があやふやで各省もバラバラなため、「社会を動かす」力も生みだせず、かえって混乱を招いているのである。 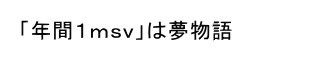 この問題について最も権威ある国際的組織はICRP(国際放射線防護委員会)だが、まずはその第3専門委員会の委員を四年間務めた中村仁信氏の考えを聞いてみよう。中村氏は現在大阪大学名誉教授であり、医療法人友紘会、彩都友紘会病院長として主にがん治療に従事されている。 氏はその著書『低量放射線は怖くない』(遊タイム出版)の冒頭、「私は、放射線の年間被曝量は100mSvまでならば健康被害はないと考えています」と言い切っている。その数字はICRPが平常時の公衆被曝限度として定める「年間1msv」とあまりに違うため、つらつらその理由を求めて読んでいくと、中村氏はICRPが以前は「閾値なし」説を採り、放射線の影響は蓄積すると考えていたため、百年の人生でも「年間1ミリ」なら100ミリを超えない(だから100mSvを単純に百年で割った数字が1mSv)、「逆に言うと100mSv以下は安心と言っていたとも取れます」と述べている(現在ではDNAの修復作用なども知られ、単純な蓄積説はとらない)。 閾値なし説とは、正式には「直線閾値なし仮説」(LNT仮説)と呼ばれるもので、疫学的データのない低線量についても、とりあえずゼロでなければ怖がっておいたほうがいいという考え方だ。いわゆる「予防医学派」は、この考え方に依拠していると言えるだろう。 放射線の影響には確定的影響と確率的影響があるが、ある線量を超えると脱毛したりする確定的影響にはむろん閾値がある。しかし発がんや遺伝的影響などの確率的影響については、長年「閾値なし」としてきたし、医師や放射線技師が学ぶ教科書にもそう書いてある。だから、やたら過敏に考える学者もいるようなのだが、じつはICRPは二〇〇七年の勧告(pub.103)で、年間100mSv以下では発がんのリスクがあるかどうかは分からない、と軟化している。 しかしそれならどうして基準そのものを変えないのか、というと、目標値としては低いのは問題ないだろう、ということと、これまでICRPの出した勧告に基づき、各国がすでに法律を作っているため、今さら変えるわけにはいかない、という理屈のようだ(電力中央研究所、元名誉特別顧問・服部禎男氏)。またこの点については、一九八六年にイギリスで発生したBSE(牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病)の判断ミスが尾を引いていると指摘する人もいる。つまりこの問題を検討したオックスフォード大学のサウスウッド教授を座長とする委員会は、「人への感染の可能性」について、「そのリスクは極めて低い」と結論づけた。ところが十年もしないうちに感染者が二百人にも膨れあがり、それによって専門家の権威は著しく失墜した。ICRPもその轍を踏まないよう、予防原則(Precautionary Principle)を崩さないというのだ。 しかし冷静に我々の日常における被曝状況を観察すれば、「年間1mSv」などという数字は夢物語であることが判るだろう。 自然界での被曝の世界平均は年間約2.4mSv。内部被曝が1.6mSvで、外部被曝が0.8mSvだが、日本の場合は家屋も石造りなどでないため、総量で年間約1.5mSvと低かった。 ここには食事によるカリウム40やもともと宇宙線に由来する炭素14の摂取も含まれる。人間にとってカリウムは必須ミネラルだが、自然界のカリウムの約0.0117%は必ず放射性のカリウム40で、体重60kgの人なら体内から約4000Bqほど発しており、それだけで年間被曝量は約0.2mSvになるという。 ちなみに今回の福島第一原発事故後、県内五十一軒の家の食事を継続的に調べたデータによれば、最も多くセシウムを摂取してしまった家でも年間0.1mSvに満たなかった(朝日新聞)。 そして住む土地の海抜が高いだけでも放射線量は増える。1500メートルで倍になる勘定だから、富士山の八合目まで登れば四倍になる。また宇宙飛行士は宇宙ステーション内で一日1mSvちかく浴びるし、普通の人が飛行機に乗った場合も、たとえば東京・ニューヨーク往復だと0.19mSvの被曝、むろんテレビからもエックス線が出ているから、週に五十時間テレビを視ていると年間では0.25mSv被曝する。 医療被曝なども考えれば年間被曝量はさらに増える。CTでは一回に6.9mSv、胃の透視では0.6mSv、歯科レントゲンでさえ0.16mSvほどの被曝である。 ICRPは、基準の前提として医療被曝は別枠だとしているが、それにしてもこうして日常を検証していくと、「年間1mSv」という数字が不可能であることは誰にでも諒解できるだろう。国によってはもともと線量が高く、イラン、ブラジル、インドの一部地域などのように、初めから年間10mSvを超える地区もある。 当初、学校の校庭などの基準を一年間20mSv」としたことに反対運動が起こり、いわば市民運動によって獲得した基準が「年間1mSv」という数字である。しかしもしかすると、この数字が今や福島県民を呪縛してはいないだろうか。特に若い親たちに、除染しても戻らない、という人々が多いのは、この現実離れした「年間1mSv」という基準のせいではないか。「安心」のための「安全」基準を厳しくしたはずなのに、かえって危険と感じる領域を増やしてしまったのではないか。 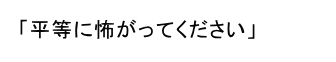 がん治療の専門家である中村氏によれば、がん細胞は、毎日誰のからだにも数千個は発生しているという。主な原因は細胞分裂の際のコピーエラーによる遺伝子突然変異とされるが、ほかに活性酸素がDNAを傷つけるケースもある。活性酸素は、普段の生活でも毎日一つの細胞あたり十億個もできており、それが数万から数十万個のDNAに損傷を引き起こすらしい。放射線を浴びるとその電離作用によって体内の水分から活性酸素が発生するが、100mSvの放射線を浴びた場合で、一日あたり約二百個のDNA損傷が起こる程度だという。 しかもそのようなDNAの殆どは修復され、たまたま修復されなかった突然変異細胞が十数個たまるとがん細胞になるというのだ。 また一旦がん細胞ができても、通常ならNK(ナチュラル・キラー)細胞やその他の免疫細胞によって駆逐される。ストレスによって副腎皮質ホルモンが発生し、それによって免疫細胞が死んでしまうことのほうが圧倒的に怖いというのである。 低線量被曝によってしか起こらない現象は、何一つない。最も多い現象は活性酸素の発生だが、この発生量も呼吸、過激な運動、ストレス、飲酒などに及ばない。「平等に怖がってください」と中村氏は言う。 二〇〇七年、マリー・キュリー賞を受賞したパリ大学名誉教授チュピアーナ博士によれば、試験管内の細胞のがん化は、200~300mSv以下では見られない。動物実験でも100mSv以下ではどの生態系においても発がんは認められない。ただ500mSv以上ではDNA修復の時間的余裕がなくなり、突然変異リスクがあがるらしい。 以上を読んでもまだ安心できない人もいるだろう。そう、問題は子供におけるリスクだと反論するかもしれない。福島県内から避難している人々の殆どが、「子供のために」県外に出たり、元居た場所に戻らないと考えているのではないだろうか。 世には、単に子供の細胞分裂が盛んであるため、それだけ何倍も危険が増すという考え(ベルゴニー・トリボンドーの法則)ばかりが溢れているように思える。たしかに放射線によって電離した電子が直接DNAを傷つけるケースも5%ほどあるらしいから無視はできないが、子供は防御能力、修復能力も高く、DNA損傷や突然変異が起きにくく、免疫細胞も元気なのである。 実際、南相馬市の原町中央産婦人科医院、高橋亨平院長は、原発事故後に生まれた子供たちの定期的な観察から次のような結論を導き、自らのブログに書いている。 「禁句のように思われていますが、子供達は大人よりセシウムに対して強い事も分かりました。傷ついた遺伝子の修復能力も、尿中の排泄能力も、からだの組織別の半減期も、数段成人より能力が高いのです。これらの事も検証していける環境も整いました。後は妨害させないように守ってやる事です」 妨害とは恐ろしい響きだが、むろん子供のほうが数倍危険だという「常識」に取り憑かれた人々による妨害、あるいは「常識」そのものの妨害と捉えていいだろう。 それにしても、以上の話がもし本当だとするなら、いったい我々の放射線についての「常識」は、以前からどれほど奇妙な方向に導かれていたことだろう。そこには、坊主憎けりゃ袈裟まで憎い式で、反原発ならば反放射能、というような感情的判断がありはしなかっただろうか。 たとえば被曝した子供の甲状腺がんは、大人に比べて二倍以上の発生率であることも今や「常識」である。しかしチュルノブイリの事故で六〇〇〇人発生したと言われる子供の甲状腺がんも、100mSv以下での発生は一例もなく、すべて1000mSvレベルの被曝者の話なのである。 中村氏は「放射線ホルミシス」についても詳しく述べている。低線量の照射により、活性酸素を消去するSOD酸素が活性化し、損傷した細胞を自爆に導く発がん抑制遺伝子であるP53も活性化し(一九九九、大西武雄氏)さらに三朝温泉地区のラドン濃度が高い場所では、キラーT細胞などの免疫機能が向上することも証明されたという(二〇〇七、山岡聖典氏)。 「放射線ホルミシス」という考え方は一九八二年、アメリカのミズーリ大学のトーマス・D・ラッキー博士によって唱えられたものだが、彼によれば人間の健康にとって最も適切な放射線量は年間100mSv程度らしく、彼は住環境の放射線量が足りないと言って、ベッドの下にウラン鉱石を敷いて寝ており、今も九十二歳で元気である。 さまざまな実験データでは、ラドン濃度3~15mSv/年での肺がんの半減、年間3~7mSvでがん死亡率15~40%減少など、年間20mSvまではむしろ健康の増進を示唆する。極めつけは一九八三年に建てられた台湾の建物のケースで、台北および周辺に建てられたアパートなど千七百軒の鉄筋にコバルト60が混入していたことが九年後の一九九二年に判明する。日本なら即取り壊しだろうが、多くの住民はそのまま住みつづけ、二十年間の疫学調査により住民約一万人のがん死亡率が激減しているのが判明するのである。 何の組織にも拘束されない私がさまざまな書籍を読みあさった結果から言えば、やはり放射線の人体への影響に絞られたそれらの研究はどう考えても無視できない。 問題はそのような専門家の多くが「御用学者」などとレッテルを貼られ、メディアで発言する機会を奪われていること。そしてむしろ専門外の人々が、エキセントリックな発言を繰り返していることではないか。 中村氏の著書から「放射線適応応答」についても触れておこう。これは予め低い線量の放射線を浴びておくと、次に大量に被曝した際のダメージが少なくなるという現象である。人間は、他の動物に比べると活性酸素処理能力が抜群に高いわけだが、低線量を浴びることでそれが更に高まるのだろう。 職業的に被曝を避けられない例えば原発作業員やパイロットなどの規制値が高いのは、そういう理由も加味されていることは知っておくべきことだろう。実際、ヨーロッパ七ヵ国のパイロット一万九一八四人の調査によれば、彼らのがん死亡率は一般人より低く、なかでも累積線量が年25mSv以上グループでは、がんによる死亡40%減という結果を示した。 ずいぶん明るい話ばかり並べたようだが、実際我々福島県人のみならず、本当に低線量被曝の影響を知りたい人々が求めているのは、この中村氏のような専門家の情報ではないだろうか。 もう一人、放射線影響研究所(放影研)理事長、大久保利晃氏の話も聞いてみよう。原爆投下の二年後から被曝者九万四〇〇〇人と非被曝者二万六〇〇〇人、合計一二万人の比較追跡調査をしてきたのが放影研だが、大久保氏は「被爆者の二世については、四十八歳までの観察では、今のところ影響は認められません」と、遺伝的影響を否定している。両親が平均400mSv被曝した子供について徹底的に調べても、ある一定の頻度での奇形の発生はあるものの、それは奇形の自然発生率よりも低かったのである。 世間の「常識」では、今回の福島県民などにも遺伝的影響を想定している。だから結婚差別なども発生するのだろう。傷ついた遺伝子によって奇形なども発生しやすいと、思い込んでいるのである。 もともとこの誤解の元は、一九二七年にマラーが行なったショウジョウバエの実験である。マラーはショウジョウバエのオスに放射線を照射し、その総量に正比例して遺伝的異常(突然変異)が増加することを確認した。これによってマラーは一九四六年にノーベル賞を受賞するのだが、後にこれはショウジョウバエの精子だからこそ起こった特殊な現象だったことが判明する。ショウジョウバエの精子は、例外的にDNA修復機能をもたない珍しい細胞だったのである。 むろん、実験が行われた当時はDNAという認識さえあるはずもなく、その修復機能も知られてはいなかった。しかもショウジョウバエの場合は総量を一遍に照射しても、少しずつ照射しても同じ結果だったため、被曝効果は累積するものと思われた。人間も同様だと思い込み、なんとICRPは一九五八年の勧告に採り入れてしまったのだ。 仕方ないといえば仕方なかったのかもしれないが、学問のそうした発展過程で犯した過ちが、面子などもあり、充分に訂正されているとは言い切れない状況なのである。基本的に、予防原則も崩さず、LNT仮説も否定はされていない状態だから、過敏な見解も出てきやすいのではないだろうか(米国科学アカデミーは今も閾値なし説を採用)。 世には涙ぐんでまで福島の危険を説き、「国に満身の怒りを表明する」児玉龍彦氏のような学者もいるが、国のやり方に対する批判は的を射ている面はあるにしても、やはり彼の正義感ゆえに不安を煽られる人々がいることも確かだ。直接P53遺伝子が傷つく危険を児玉氏は訴えるが、活性化する分との差引勘定について、専門家どうしでじっくり検討してもらえないものだろうか。また児玉氏が指摘する「チェルノブイリ膀胱がん」の危険についても、確率的影響の範囲を超えて聞こえるのが問題である。 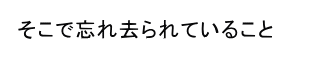 児玉教授が除染の支援をしている南相馬市で、今年一月二十七日、ホールボディカウンターによる内部被曝調査件数が一万人を超えた。その診断結果が発表になったのだが、それによれば、小・中学生七九名、高校生以上四七四五名のうち、小・中学生では検出限界以下(ND)三六一名、検出者二一八名のうち二一四名は20Bq/kg以下。20Bq/kg以上は四名、30Bq/kg以上は一名、40Bq/以上はなし、という結果である。高校生以上の場合は、ND二八〇二名、検出者一九四三名のうち一七七四名が20Bq/kg以下、20Bq/kg以上は一六九名、30Bq/以上は六八名、40Bq/kg以上は三一名、50Bq/kg以上は一六名であった。最高値は110.7Bq/kgだが、この人の五十年預託実行線量だけが僅かに1msvを超え、1.069mSvである。しかも再検査を実施した二〇名のすべてが再検査では放射線量が減少している。 このお知らせを下さった東大医科学研究所の上昌広教授は、「殆んど内部被曝はありません。良い感じになってきていますね」とメイルを結んでいる。 同じ南相馬に出入りする児玉教授の説く『内部被曝の真実』とはいったい何だろう。たしかに貴重な資料や提言を含んでおり、今後起こるセシウムの濃縮についても考えさせられるが、あまりに見方が悲観的に過ぎないだろうか。 思えばこうした見方は、現在の医療界では一般的だったことを憶いだす。インフォームド・コンセントと称し、たとえば手術前には最悪のことまで話そうとする医者ばかりになりつつある。 人間の心理やストレス生成の在り方など、そこでは忘れ去られていると思わざるを得ない。 たしかに原爆被曝者の場合、200mSvを超えた被曝者から白血病の患者が線量の増加に伴って有意に増えた。十年後には甲状腺がん、十五年後には肺がん、乳がんが見られるようになり、二十年で胃がん、大腸がんが一般の人より多く発病している。しかしこれだけ長期間経ってからの発病を、放射線のせいと断定することが果たして可能なのだろうか。私には「被曝者」として生きなくてはならなかったストレスのほうが、何倍も悪影響を及ぼしていたように思える。 どうか福島に生きることを、これ以上ストレスにまみれさせないでいただきたい。日本人の約30%ががんで死亡する現在、それがコンマ数%増えるとしても針小棒大に騒がないでいただきたいのである。 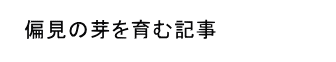 二〇一二年二月三日、イギリスの「The Independent」という雑誌のウェブ版トップに、「福島原発界隈、鳥が急減」という記事が載った。これは日本、デンマーク、アメリカの研究者たちの共同研究だが、後日発表になった論文を読むと、福島県内の三百地点で昨年七月、目視と鳴き声観察を行なったところ、チェルノブイリと共通する鳥十四種類について個体数の減少が見られたというのである。比較は詳細にわたるが、概してはツバメの線量に応じた個体数の減少、渡り鳥として越冬地と汚染地域を行き来する際、汚染地域で主に数が減ること、また色が抜けたり尾の長さが違ってしまうなど、体の異常についても報告されている。他の鳥にも共通なのは、脳の体積の減少である。また「ヒタキ」という鳥では、低線量の地域を選んで巣を作るとも分析されている(ちなみに福島県の県鳥はヒタキの仲間のキビタキ)。 こんな記事や論文を、何の予備知識もなく読まされたら誰でも驚き、さまざまな邪推で悲観的になるに違いない。 実際この記事の英語版のサマリーには、「福島では放射線にさらされてから間もない弟一世代の『動物(animals)』に、すでに放射線の負の影響が出始めている」と書かれている。悪気はないのかもしれないが、animalsは言い過ぎである。 NHKのBS番組「被曝の森はいま」でも放送されたことだが、チェルノブイリの森に住む動物たちは科学者たちの予想に反し、奇形やがんもなく、数も増やしていた。しかし唯一の例外がツバメなどの渡り鳥だったのである。 渡り鳥が遠い海を越えて飛んでくるのはかなり過酷な運動であるため、大量の活性酸素がすでに発生している。到着して普通に休むことができればそこでDNA損傷も修復され、回復するのだろうが、あろうことかその時点でまた被曝し、さらなる活性酸素が出てしまう……。小さな壜に入れたハエと大きな壜に入れたハエでは、小さな壜のハエのほうが長生きする。それほどに、活性酸素は寿命に影響を与えるのである。また鳥類の多くが尿と糞と一緒の固まりとしてしか排出できないことも事態を悪化させている。餌として啄む木の実などによる内部被曝を、彼らは尿として単独には排出することができないのである。 キャッチーな記事を求めるのはメディアの常かもしれないが、こうした記事が人々の誤解を膨らませ、偏見の芽を育むのではないか。 個人的なブログやツイッターなども含めれば、悪意さえ感じる情報に遭遇することもある。鼻血を出す子供、生まれつき耳がない猫の写真なども、その類のゴシップに過ぎない。ただこうしたケースの多くも、悪意ではなく本人が本気で信じ込んでいることもあり、これが更に困るのである。 ある程度の知識をもたなければその手の偏見さえ笑い飛ばすことはできない。間違った考えでも複数の人間に言われればそんな気にもなる。今の福島県民は、概ねそういう状況なのである。そんな状況から福島県民を救いだすのは、専門家の役目ではないのか……。  もう一度放影研の大久保氏の言葉を紹介しておこう。 大久保氏は名古屋での講演で年間20mSvという基準について聴衆に質問され、以下のように答えている。 「20というのは悩ましい数字なんですね。さっき申し上げたように、これはそれほど高い値ではありませんので、私がそこに住んでいる本人であれば、短期間であれば様子を見ましょうという話になると思います。結局はどれだけのエネルギー、費用をかけて今すぐやるべきなのか、後でもいいのかという話なので、これは決める権利のある当事者が納得して決めるべきことです」 確かにそれはそうなのだが、私には専門家であるはずの人の及び腰ばかり気にかかる。 その講演会場では質問者が瓦礫処理について、財政との絡みも気にしつつ次のように言う。「老人ホームをつくって、そのそばに瓦礫を置けば膨大な土地を政府が買い上げんでも済みます。そんなことを素人が考えておりますけど、ご意見を」と求められ、大久保氏は「大賛成です。そのとおりだと思います」と答えている。 「ですから、例えば牛肉でも、汚染量を測って、その数値を値段の横につければいいんじゃないかと思います。今ご質問をいただいたので、ここならこういうことを言えますが、もし、公的な場で放影研の理事長という肩書きでそれを言ったら、翌日の新聞の第一面に必ず出ます。今後そういう主張をするかどうかは、ちょっと考えさせていただきたいと思います」 大久保氏が講演されたのは昨年の十一月二十八日だが、その後、充分お考えいただいただろうか。 どうか現在の風潮に、専門家として一言、公的な場で発言していただけないだろうか。 現在の「年間1mSv」という基準を目差すかぎり、県内のコミュニティの再生はおそらくあり得ない。若者や子供のいない町は成り立たないはずである。 老人ホームの話は、いくら何でも言わないほうがいいかもしれないが、やはり専門家として、もう少し現実的な提言をしてほしい。何十年後かに指摘されるかもしれない発がんリスクまで含めれば、責任はとれないということなのだろうが、少なくとも福島はそういうレベルではないのだと明言し、今のストレスフルな福島生活に一石を投してほしいのである。そうでなければ放射線影響研究所の名が廃るではないか。 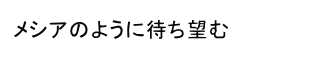 最後にICRPの「アララの原則」に触れておこう。 ICRPの予防原則は、できる限り(放射線量を)低く、とは言われるが、その文章の後半には「As Low As Reasonably Achievable」(ALARA)と書かれている。つまり「合理的に実現可能なだけ低く」とは、資金、社会的影響、なども考えたうえで「できる限り低く」なのである。 しかもこの原則は、復旧期の「年間1~20mSv」について、20mSvで満足せず「防護の最適化」を目指そうという話だ。 福島県内ではすでに、各地で除染実験も行なわれたが、夏頃とは違った様相を呈している。単純に高圧洗浄などをしても線量が下がらない場所が多く、屋根の張り替えや道路の掘削をしなければならないだろうとも言われる。しかし道路を削れば、また吸引によって内部被曝する可能性も出てくる。場所によっては除染活動後、線量が上がった地域まであり、特に行政の人々は頭を抱えているのである。 むろん、仮置き場や中間貯蔵施設が決まることが除染活動の大前提になる。その上で、たとえば我が三春町の規模でも、全域の除染には百億円ほどかかるとされ、県内全域では三千億円以上が予算化されている。 無尽蔵にお金があるわけじゃないから消費増税が取り沙汰されるなかで、いったい何が「Reasonable」なやり方なのか、専門家どうし膝を突き合わせて話し合うべきではないか。むろんその際に、県民の健康を最重視する姿勢を崩すべきではないのは言うまでもない。その上で、トーマス・D・ラッキー教授は日本に対し、「呉々も無駄なお金を使わないように」と呼びかけているというのだ。過敏派も、それを無視するだけでなく、泣かずに反証してほしいのである。 二〇〇八年九月に日本学術会議に提案された定義によれば、「『安心』とは、(安全であり、かつ)安全であることが信じられること。『信じられる』とは、理解できるか、説明内容ないし説明者が信頼できること」とされる。 福島県民は、いま切に安心を求めている。現実的で冷静で、矛盾のない説明者の出現を、メシアのように待ち望んでいるのである。 |
||
 |
||
| 「新潮45」2012年4月号 | ||
| 第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 | ||
| |
||