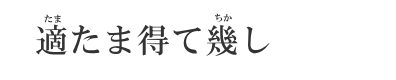 |
||
| このところ、長寿を目指すさまざまなココロミが盛んである。医療の進歩はありがたいことだが、そこに留まらず、食べ物もそうした基準で選び、さらには月に数万円分ものサプリメントを飲む人までいる。今や長寿は「欲望」の対象になりつつある。 諸子百家をある種の技術者集団と捉えるならば、老子・荘子を祖として仰ぐ道家は、長寿の技術者たちだという見方もある。なるほど老子は二百歳以上生きたとも言われるし、荘子も長寿を否定はしない。 しかし否定しないということが、即ち目指していいと思うのは浅慮である。結果として長生きすることは褒められるが、それを目指すのはあまりに下品だし、 荘子は、 恵施というのは『荘子』に何度も登場する友人だが、論理学派(名家)に属し、しょっちゅう荘子に問答をしかけていた。荘子は常々「聖人にはいわゆる人情がないため、是非に囚われることがない」などと主張していたため、「情がなくてどうして人間と云えよう」と恵施が突っかかった。それに対し荘子が、「情」というのはそういう意味じゃなくて、自分の是非や好悪による判断の、「是」や「好」のほうを助長しようということだと述べる。それが「益す」ということでもあり、そんなことをすると、是非や好悪の感情によって気持ちが乱れ、精神を損なう。だから常に自然に因りて、生を益さざれ、非人情であれ、というのである。 『老子』第五十五章には、「生を益すこと 鎌倉の円覚寺居士林で参禅した夏目漱石は、『草枕』の主人公にこの「非人情」の境地を託す。 かうやって、 ここで「之」と呼ばれるのは、明らかに「淵明、王維の詩境」と同意だが、おろらくはあらゆる思惑を離れた自然な在り方を、漱石は主人公の画工に、春の山路の自然から吸収させようというのである。 陶淵明も王維も、『荘子』や禅に親しんだ詩人である。陶淵明は「帰去来の辞」の最後にこう記す。「 自分の思いを意志的に遂げるのではなく、変化に乗じてされるがままを楽しみ、自然と一体化する。天明が尽きるまでそんな在り方を続けよう、疑うまい、ということか。 あくまで受け身、それも強靭なまでの受け身の姿勢と云えるだろう。仏教ではこの姿勢をとうとう観音の思想にまで高めた。状況の変化に応じて自らを無限に変化させ、それを楽しもうという態度である。 たとえば住居や食べ物に関して荘子は、「夫れ聖人は 食べ物に関して云えば、それはお釈迦さまが一生托鉢で頂いたものしか食べなかったことにも通じる態度だろう。 たしかに客として出された食べ物に向き合うには、それこそ究極の態度であるように思える。しかしもてなす側としてはどうなのか……。 このほうがあの人は喜んでくれるだろう。こっちのほうが体にもいいのではないか。そんな「生を益す」発想、「情」を捨てるのは難しかろう。取捨選択こそ心を乱し、もちまえを歪曲する(天地篇)というけれど、それでは亭主も務まらないではないか。 じつはそれを救うのが「 お菓子も長寿も、適たま「ご縁」で得てこそありがたいわけだが、この「適たま得る」頻度が増えていくことこそ、修行の成果なのかもしれない。 |
||
 |
||
| 「なごみ」2011年3月号 | ||
| |
||
| |
||